 |
 |
| 日本大学 泉 龍太郎さん | 産婦人科医師/医事法学研究者 江澤 佐知子さん |
 |
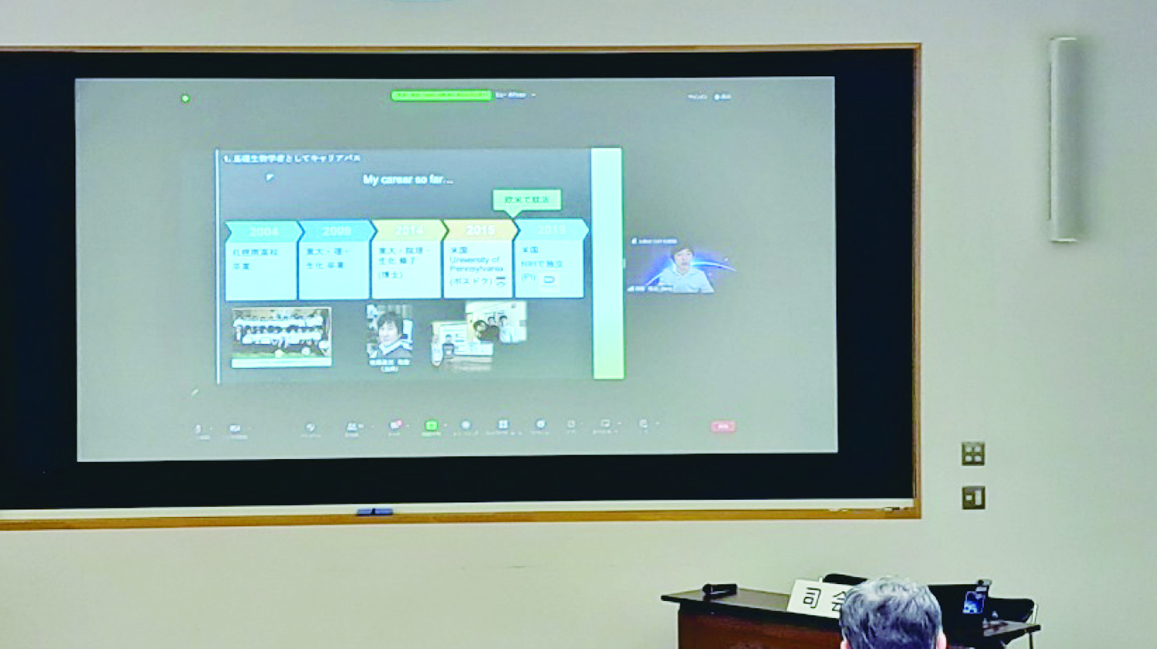 |
| JAXA 内山 崇さん | アメリカ国立衛生研究所 明楽 隆志さん |
 |
 |
| 筑波大学大学院 有屋田 健一さん | 司会者 暮地本 宙己さん,速水 聰さん |
宇宙航空環境医学 Vol. 61, No. 2, 87-94, 2024
開催報告
令和5年度 日本宇宙航空環境医学会 宇宙基地医学研究会 開催報告
宇宙基地医学研究会 世話人一同
令和5年度の日本宇宙航空環境医学会 宇宙基地医学研究会は,令和6年2月16日(金)の18時より,西新橋に位置する東京慈恵医科大学南講堂と,オンラインのハイブリッドで開催しました。現地およびオンライン参加者を含め,全体で161名(世話人,演者,ボランティア含む)の申し込みがありました。また32名の会員の方に宇宙航空医学認定医のポイントを付与することも出来ました。研究会終了後は,現地参加者同士が交流する懇親会を開催し,今回のテーマに関する宇宙飛行士選抜関連の話題以外でも非常に盛り上がりました。なお,添付4のアンケート結果より,会の運営に際してZoomでの音声が聞き取りにくいという声があり,次回以降の検討課題としたいと思います。次年度以降も,本研究会は新たな活動を続けて行く予定です。ご意見・ご要望がありましたら,是非お寄せ下さるようお願いします。
【プログラム】
テーマ:宇宙飛行士への挑戦〜日本人宇宙飛行士選抜試験を受けて,その後の人生〜
目的と概要
今回の宇宙基地医学研究会は,過去の日本人宇宙飛行士選抜試験受験者が選抜試験を経て人生観をどう変え,その後の人生に活かしてきたかをご発表いただきます。宇宙医学分野におけるキャリア形成のあり方についての議論に繋げて行くことを目的としています。
日時:令和6年2月16日(金)18時〜20時
場所:東京慈恵会医科大学(高木2号館地下1階)(東京),及びZoomオンライン
1. 1991年の応募者
泉 龍太郎(日本大学)
2. 2008年の応募者
江澤 佐知子(医療法人健正会・早稲田大学大学院)
内山 崇(JAXA)
3. 2022年の応募者
明楽 隆志(アメリカ国立衛生研究所)
有屋田 健一(筑波大学大学院)
司会 暮地本 宙己(東京慈恵会医科大学),速水 聰(JAXA)
研究会世話人:泉 龍太郎(日本大学),有屋田 健一(筑波大学大学院),井上 夏彦(JAXA),大本 将之(久留米大),寺田 昌弘(京都大学),速水 聰(JAXA),暮地本 宙己(慈恵医大)
添付1:抄録集
添付2:会場の写真
添付3:アンケート結果
添付1:抄録集
1. 1991年の応募者
『夢破れて宇宙あり』
泉 龍太郎(日本大学)
【背景と経緯】
立花隆氏の古典的名著である「宇宙からの帰還」に魅せられ,宇宙に関心を持つようになり,宇宙に行ってみたいという気持ちが生じた。視力の問題もあり,正直,宇宙飛行士の資質を満たしているとは思えなかったが,1991年に実施された第2回目の日本人宇宙飛行士選抜(当時33歳)では,第2次選抜まで残ることができた。それ以上進むことは叶わなかったが,その時の縁を機に,後日,宇宙関係機関に所属し,宇宙医学・生命科学研究を推進する業務に従事することとなった。ただ当時は,医学・生命科学分野の中では「宇宙」は極めてマイナーな立場であり,また宇宙関連業界においても,医学・生命科学は,非常に特殊な領域と見做されていた。その後,国際宇宙ステーションが軌道に乗り,日本人宇宙飛行士も定常的に滞在し,また宇宙における医学・生命科学実験も重要な位置を占めるようになり,隔世の感を有している。最近はMoon Village勉強会での活動を踏まえて,人類社会の将来像に想いを巡らすことも多く,地球を離れた宇宙環境に人類社会が実現するのも,そう遠い未来の話しではないことを実感している。
【演者プロフィール】
1985年九州大学医学部卒業後,大学院在学中に第2回目の宇宙飛行士選抜を受ける。その後,1993年に(財)宇宙環境利用推進センターに転職,1998年より宇宙開発事業団(現:宇宙航空研究開発機構)に移り,宇宙医学・生命科学研究に関わる業務に従事,最終的には向井千秋飛行士(室長)の下で,宇宙医学生物学研究室の研究員を勤める。2009年から日本原子力研究開発機構(大洗研究開発センター)の専属産業医を経て,2013年よりJAXA(当時は宇宙開発事業団)のFSであった宮本晃先生の後任として,現職に着任。日本大学は本年3月で定年を迎えるが,宇宙との縁はまだまだ切れそうにない。
2. 2008年の応募者
『競争でなく‘協調’,その後の学びの人生』
江澤 佐知子(医療法人社団健正会,早稲田大学法学研究科後期博士課程)
【背景】
2008年,JAXA宇宙飛行士選抜試験に女性唯一のファイナリストとして挑戦した。個人的な学びは,競争でなく‘協調’であった。
【目的】
選抜試験を終えて,その後の自らの人生を概観し,その学びについて報告する。
【過程】
テクノロジーと生殖という課題は,選抜試験以前から私の大きなテーマであった。検討の1つとして,臨床医からみて「法律を整備することで救われる命があるのではないか」というジレンマに向き合うべく,臨床の傍ら2012年より法学部で法学を学び始める。卒業後,双子男児の出産を経て,2017年早稲田大学法学研究科後期博士課程へ進学し,生殖医療を医事法の視点でサポートする研究に取り組み,2024年2月に法学博士論文として集成した。
医学技術,とりわけ人間の生殖に関する技術の進展はめざましく,本来私ごとであった子どもを産むことに関して,従来の法的思考枠組みを超えるほどの進歩を遂げつつある。生殖補助医療技術や出生前診断の進歩の速さやそれに伴うわれわれの意識変化によって技術が先行し,法律が後追いになる場合もあり,生殖法の拡充に関して日本はその岐路に立たされている。
「生殖の自由」は,憲法,家族法,刑法など様々な法領域に関係するが,それらの法領域にまたがる医事法の観点からも重要な問題領域とされている。机上の論理的アプローチも重要であるが,産科における臨床実務経験と医療現場の実情を上記の諸問題に照らし合わせ,統合的に本研究に反映させることで,また各専門を持つ者同士が協力しあい統合的な議論が活発化することによって解決の方向性を模索することが統合的医事法の視点として重要であった。
【結語】
人生には数多くの学びの機会があるが,単に専門性を追求することや多角的視野を持つだけではなく,統合的思考を持つことによって互いが協調し,他分野の専門家とも,そして社会とも協調をすることで,科学技術・医学技術の進歩に一定の規範的コントロールとの両輪が可能になり,初めて平和利用ひいては,人類の福祉に役立つものである。
【プロフィール】
2008年に慶應義塾大学にて医学博士を取得した年に,JAXA宇宙飛行士選抜試験を受験する。その後は,産婦人科臨床医として従事。2012年早稲田大学法学部に学士入学,医療と臨床実験に関する研究が,早稲田大学法学会懸賞論文賞を受賞,2014年に双子男児の母となった年に卒業。2017年同大学法学研究科後期博士課程へ進学し,生殖医療と医事法に関する研究を進める。その他,現在,南流山レディスクリニック顧問,International Schoolの産業医,Harvard University based IVF research company顧問,TBS番組審議委員副委員長等を務める。
2. 2008年の応募者
『宇宙飛行士選抜への挑戦 〜挑戦から得たもの〜』
内山 崇(国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 有人宇宙技術部門)
・宇宙飛行士になりたいと思ったきっかけ
10歳の時に見たチャレンジャー事故をきっかけにスペースシャトルにあこがれ,大人になったら宇宙開発をやりたいと思うようになった。
・宇宙飛行士選抜のタイミングと選抜過程
学生時代に日本人でも宇宙飛行士になれる時代となり,社会人になって経験を積んだら数回はチャレンジしたいと思っていた。民間企業で宇宙ステーション補給機(こうのとり)の開発業務に従事。しかし,コロンビア事故・ISS建設の状況から1998年に3人選抜したあとの選抜が行われない実状を知っていた中で10年が経った。「きぼう」「こうのとり」の打ち上げが迫る中,先んじて2008年2月に募集が発表されたときは正直驚いた。奇しくも,JAXAへ転職したタイミングであった。
「こうのとり」フライトディレクタ候補として訓練中であり,有人基地にランデブする宇宙船の運用指揮を執れる能力を磨くことが,宇宙飛行士に必要な能力にもつながる。そのため,仕事と選抜に向けた準備の両輪がどちらも両方にダイレクトに生きた。宇宙飛行士になって何をしたいか?については,『日本の有人宇宙開発を前に進めることに宇宙飛行士として大きく貢献したい』。また,どういう日本人宇宙飛行士が求められているか?を徹底的に追及し考え抜き,それに一歩でも近づけるよう努力した。
・宇宙飛行士選抜挑戦から得たもの:
✓指先まで届いた人生をかけた夢への挑戦が,最後の最後でこぼれ落ちてしまった体験と,長い時間をかけて自分の中で消化しながら,違うルートから同じ夢を追い続けるに至る貴重なカムバック経験
✓挑戦に失敗なんてものはなく,それを未来にどう生かしていくかが全て
✓同じ夢を持った同志であり,刺激を与え合い続ける良きライバルとの出会い
夢を抱き育み,夢に向かって努力し,本気の挑戦をしたからこそ得られたかけがえのない経験から,大きな人生の財産を得ることができた。
【演者プロフィール】
2000年に東京大学大学院修士課程修了後,(株)IHI入社,宇宙ステーション補給機「こうのとり」の開発に従事。2008年にJAXAへ転職し,「こうのとり」フライトディレクタとして,9機連続ミッション成功に貢献。現在は,新型宇宙船開発に従事。
3. 2022年の応募者
『基礎生物学からみた宇宙への道』
明楽 隆志(アメリカ国立衛生研究所)
【要旨】
私は2022年から2023年にわたり実施されたJAXAの宇宙飛行士候補者選抜に,海外から応募しました。これまで宇宙開発とは無縁だった経歴を持つ私がなぜ選抜に挑戦したのか,選抜過程での心理的変化についてお話しします。また,選抜試験を経験して得たものと,今後のキャリアへの影響についても考察します。
1. 基礎生物学者としてキャリアパス
私が科学者を目指した背景と,博士号取得後にアメリカへ渡った理由,さらに海外での独立を決意した経緯など,私のキャリアパスについて詳しく紹介します。
2. 第六期 宇宙飛行士候補者選抜
選抜試験はオンラインでスタートしましたが,次第に他の受験者との交流が増え,競合するはずの彼らとの間に仲間意識が芽生えました。また,選抜が進むにつれ,研究者としてのキャリアを終える可能性も現実味を帯びてきました。特に二次選抜と最終選抜を経て感じた心境の変化に焦点を当てて話したいと思います。
3. 宇宙医学研究への挑戦
選抜終了後,宇宙への夢を諦めず,宇宙開発への貢献を模索しました。生物学者としてのスキルを活かす道として,宇宙医学の分野で貢献する可能性があります。NASAには,宇宙における医学・生物学実験の基礎を学ぶ研究プログラムがいくつもあります。これらのプログラムを紹介しつつ,基礎生物学者がアルテミス世代の宇宙医学にどう関わっていけるかについても探求します。
【演者プロフィール】
2014年に東京大学大学院の理学系研究科,生物化学専攻で博士号を取得した後,アメリカのペンシルベニア大学で博士研究員として勤務しました。2019年にはワシントンD.C.郊外にあるアメリカ国立衛生研究所(NIH)で自身の研究室を開設し,マウスモデルを用いてSelfish DNAと不妊との関連性について研究を進めています。2022年から2023年にかけてはJAXAの宇宙飛行士候補者選抜を受験しました。2023年にはNASAのSTAR (Spaceflight Technology, Applications, and Research)プログラム,2024年にはNASAのSHINE (Space Health Impacts for the NASA Experience)プログラムの一員に選ばれ,宇宙医学研究のための基礎トレーニングを積んでいます。
添付2:会場の写真
 |
 |
| 日本大学 泉 龍太郎さん | 産婦人科医師/医事法学研究者 江澤 佐知子さん |
 |
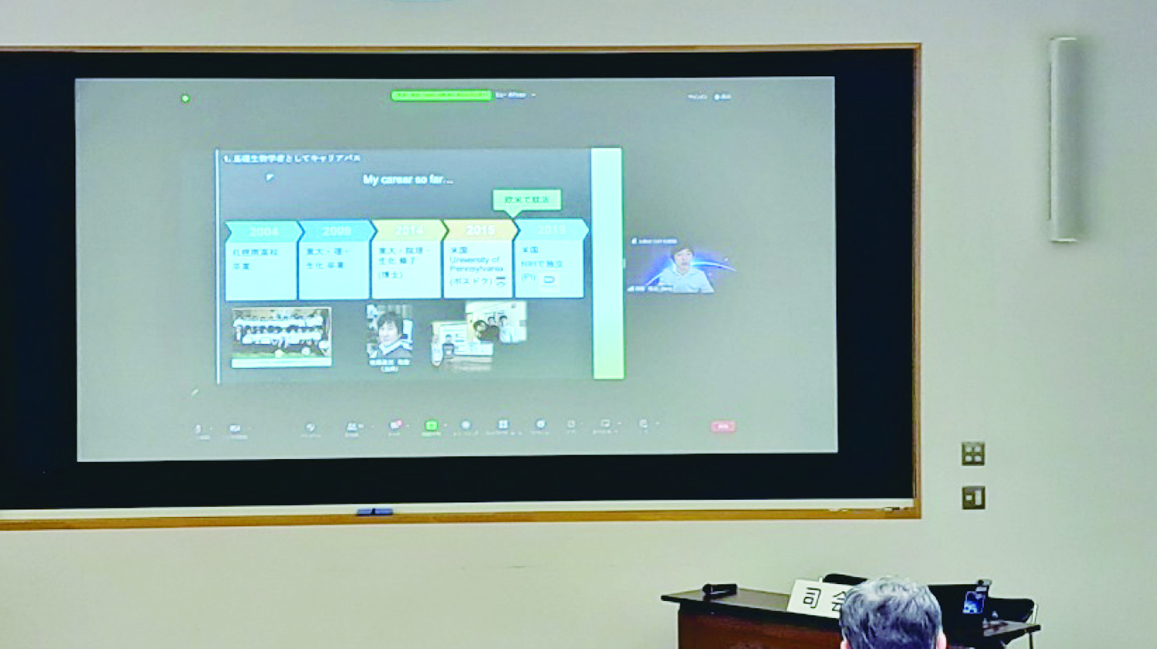 |
| JAXA 内山 崇さん | アメリカ国立衛生研究所 明楽 隆志さん |
 |
 |
| 筑波大学大学院 有屋田 健一さん | 司会者 暮地本 宙己さん,速水 聰さん |
添付3:令和5 年度 宇宙基地医学研究会 アンケート結果
32 名回答,重複・類似の回答は整理した
1. 研究会の内容について
| 非常によかった | 24 |
| よかった | 7 |
| どちらでもない | 1 |
| つまらなかった | 0 |
| 非常につまらなかった | 0 |
2. 研究会で印象に残った点
医療系でない宇宙飛行士選抜ファイナリストの話(2)
医学研究会でありながら他分野の情報提供
宇宙飛行士の選抜試験について聞けた(3)
宇宙飛行士を目指した後のキャリア形成について(2)
学会員でなくても自由に参加できて良かった
総合討論の場があると良い
フライトサージャンという選択肢があるという事がわかった
3. 講師にお伝えしたいこと
選抜方法の改善についての意見を述べるべき
4. 今後の宇宙医学研究の取り組みに関する提言
宇宙医学研究の再生,宇宙医学研究の体系的な取り組み
低重力環境が幼児の成長にどのような影響を与えるかに興味があります
5. 今後の宇宙基地医学研究会の活動で,取り上げてもらいたい話題
民間宇宙飛行に対し,医学的な観点からの各社の取り組みなどを知りたい
ヒト対象研究のIRB体制の解説
国外で活躍する宇宙医学関係者の話題
Gateway時代の実験や医学的な考察
月面や火星における,Partial gravityでの医療や実験の考察
宇宙の女性進出に関して
フライトサージャンの話題
宇宙医学ガイドライン作成について
6. 今後の日本宇宙航空環境医学会の活動として,期待すること
民間宇宙活動に関する支援
学会サイトの刷新
7. その他(会の運営に関して)
Zoomでの音声が聞き取りにくかった(5)
会場が分かりにくかった
学会員以外にもオープンな企画で興味深かった