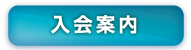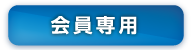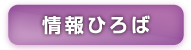HOME > 最新例会抄録 > 感染症の病理診断 -特殊染色、免疫染色に求めるもの―
感染症の病理診断
-特殊染色、免疫染色に求めるもの―
-特殊染色、免疫染色に求めるもの―
比島恒和
がん・感染症センター都立駒込病院 病理科
感染症診断の主役は各施設の微生物検査部門であるが、そこでの検出困難な病原体の証明を病理で補完することがしばしば可能である。生検、手術材料や細胞診検体での感染症の病理診断結果は患者の治療法に直結する有用な情報になりうるし、剖検例で感染の状態が明らかにされれば病態の理解や生前の治療法の検証にも役立てられる。感染症診断における病理の強みの一つは、直接病原体を観察できなくとも、病原体に対する組織の反応から原因微生物を推定できるところにある。例えば、壊死性肉芽腫性炎をみれば抗酸菌感染症が疑われるし、封入体や融合細胞を形成する像からはウイルス感染が示唆される。後者のようにHE染色のみで病原体がほぼ推定できる疾患もあるが、多くの症例では特殊染色(グラム染色、グロコット染色、抗酸菌染色、ギムザ染色、PAS染色等)を活用する。古典的な特殊染色は病原体を同定する染色ではないが、感染の有無の確認や起炎菌の絞り込みにしばしば有効であるため今なお感染症診断における必須アイテムである。したがって各施設における基本的な染色法の習得と精度管理は重要である。一方、免疫染色は微生物の同定に極めて有用であり、特にウイルス感染症では威力を発揮する機会が多い。本講演では、特殊染色や免疫染色で検出可能な感染症症例を具体的に提示しながら、それらの染色の有用性と問題点に関して概説する予定である。