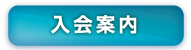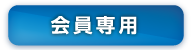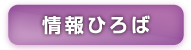HOME > 最新例会抄録 > 病理組織検体を使用した遺伝子関連検査の精度向上 ―明日からできる効果的な方法―
―明日からできる効果的な方法―
永谷 たみ
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 臨床遺伝子医療学
日本赤十字社姫路赤十字病院 臨床検査・ゲノム検査科
2019年6月に保険収載されたがん遺伝子パネル検査では、病理組織診断に使用されるFFPEから作製した未染色標本を用いて検査が実施されている。がんゲノム医療中核拠点病院・拠点病院・連携病院で、患者一人ひとりのゲノム解析の結果得られた配列情報や診療情報は、がんゲノム情報管理センター(C-CAT)に集約・保管し、利活用されている。2025年3月には登録者数が10万人を超えた。
がんゲノム検査を含む遺伝子関連検査の種類や提出件数は増加の一途をたどっており、検査に携わる臨床検査技師の重要性も高まっている。特に、解析を外部機関に委託する施設が多い現状では、技師が関与する前処理工程が重要である。検査精度を左右する要因として、検体の固定やFFPEの作製、未染色標本の作製といった取扱いがあり、提出基準を満たす標本の作製は、技師の技術と判断力に委ねられている。また、病理医が検体の適格性評価や、FFPEの選定などを適切に行えるよう、検体の状態や処理工程の情報を正確に伝えることも技師の重要な役割である。
しかし現場では、「この方法で正しい結果が得られているか」「どこまでやれば十分なのか不明確」といった不安の声が多く、検査結果に関するフィードバックも限られるため、標本の質と結果の関連が見えにくいのが実情である。
本講演では、以下のポイントを中心に解説する。
・遺伝子関連検査の流れと、提出検体に求められる条件の理解
・検体ごとに適した標本作製と、避けるべき注意点の整理
・コンタミネーションリスクを最小限に抑えるための工夫
・標本作製技術の精度を評価・管理するための現実的なアプローチ
組織を採取する臨床医、検体作製を担う技師と、それを診断・評価する病理医の3者が連携することで、より信頼性の高い検査が実現する。3者の協働が検査精度を支えるという視点を共有し、岡山大学大学院と姫路赤十字病院での実践をもとに、明日からの業務に自信をもって臨むためのヒントをお届けする。