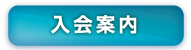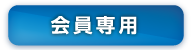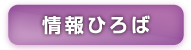HOME > 例会抄録 > 第112回日本病理組織技術学会 > 膵病変の病理診断
平林 健一
富山大学学術研究部医学系病理診断学講座
膵病変の病理診断は、検体の採取方法や種類によって主たる診断対象が異なる。たとえば、膵液や膵管擦過検体では、浸潤性膵管癌、膵管内乳頭粘液性腫瘍(intraductal papillary mucinous neoplasm:IPMN)、膵上皮内腫瘍性病変(pancreatic intraepithelial neoplasia:PanIN)など、膵管由来あるいは膵管に関与する病変が主な対象となる。一方で、粘液性嚢胞腫瘍(mucinous cystic neoplasm:MCN)、漿液性嚢胞腫瘍(serous cystic neoplasm:SCN)、充実性偽乳頭状腫瘍(solid pseudopapillary neoplasm:SPN)など、膵管との関連性が薄い病変は、基本的には対象外となる。
近年では、膵管鏡を用いたマッピング生検の導入も進んでいるが、膵液・膵管擦過検体においては、依然として細胞診が主たる診断手段である。施設によっては、診断精度の向上を目的として連続膵液細胞診(serial pancreatic juice aspiration cytological examination:SPACE)も試みられている。一方、超音波内視鏡下穿刺吸引・生検法(endoscopic ultrasonography-guided fine needle aspiration/biopsy:EUS-FNA/B)による検体では、主に充実性病変が対象であり、MCN、SCN、IPMNなどの嚢胞性病変の多くは穿刺の適応外とされる。
EUS-FNA/Bにおいては、迅速細胞診(rapid on-site evaluation:ROSE)が広く普及しているが、近年では、肉眼的に採取検体を評価するMOSE(macroscopic on-site evaluation)を導入する施設も増加している。切除標本の病理診断においては、術前化学療法に対する治療効果判定が重要な評価項目となっている。そのため、膵頭十二指腸切除検体においては、術前画像との対比を可能とするよう、十二指腸乳頭部開口部を通るKerckring皺壁に平行な断面(いわゆるCT断)での切り出しが推奨される。一方、膵体尾部切除検体では、膵の長軸に直角な断面での切り出しが推奨される。また、膵癌取扱い規約第8版においては、腹腔洗浄細胞診陽性例が遠隔転移として扱われるようになり、その臨床的意義が一層高まっている。本講演では、膵病変の病理診断における診断アプローチと、切除検体の切り出し法等について概説する。