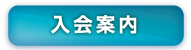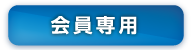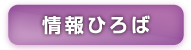HOME > 最新例会抄録 > 当施設におけるアミロイドーシスに対する免疫組織化学染色の運用
佐藤 孝之
慶應義塾大学医学部 病理学教室
アミロイドーシスは、アミロイド線維が組織に沈着し、さまざまな臓器機能不全を引き起こす疾患群である。全身性アミロイドーシスと限局性アミロイドーシスに分類され、アミロイド蛋白の種類によって臨床病型が決定される。厳密には生化学的解析が理想的であるが、日常的に行うのは困難であるため、多くの病理検査施設では免疫組織化学染色(免疫染色)が行われている。
病理組織標本では、Congo-red染色と偏光顕微鏡下でのアミロイド沈着の確認後、免疫染色による病型判定を行う。日本国内でみられる全身性アミロイドーシスの多くは、AL(κ,λ)、AA、ATTR、Aβ2Mのいずれかであり、一次抗体として抗免疫グロブリンL鎖(κ,λ)抗体、抗AA抗体、抗トランスサイレチン抗体、抗β2ミクログロブリン抗体が診断に用いられる。
しかし、免疫染色による病型判定には課題が多い。特にAL(κ,λ)アミロイドーシスやATTRアミロイドーシスに対して、市販抗体では前駆蛋白に陽性を示すことに加え、アミロイド蛋白は立体構造の変化により染色性が不安定となり、結果の解釈が難しいことが知られている。
当施設では2019年より、「厚生労働省アミロイドーシスに関する調査研究班」により作製された抗体(抗κ抗体、抗λ抗体、抗トランスサイレチン抗体)を含めた抗体パネルを用いた運用を行っている。これらの抗体は市販抗体と比較して、前駆蛋白に対する反応性が弱く、アミロイド蛋白には良好な染色性を示す。本発表では、当施設におけるアミロイドーシスの病型判定に関する免疫染色の実際と運用方法を紹介する。さらに、同研究班の活動内容や他施設での免疫染色の運用状況についても報告する。