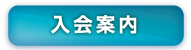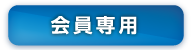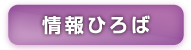悪性リンパ腫の総合病理診断
【質問事項】1.リンパ腫診断における形態所見と分子診断(FISH,PCR,NGS等)の役割について,現時点でのバランスや活用法をご教示ください.
2.血液疾患に対する遺伝子パネル検査について,クロット検体と新鮮検体のどちらが推奨されるか,また学会報告や最新知見をご教示ください.
3.READ systemを利用した場合の患者さんへの検査料請求の取り扱いについて,現状をご教示ください.
4.READ systemに関連し,CTガイド下生検の検体取り扱いにおいて必要な腫瘍細胞量や,注意すべき点があればご教示ください.
【回答】
1.まずはフローサイトメトリーと形態,免疫組織化学により診断するのが基本となっています.FISHはさらに細分類を要し,例えばBurkitt lymphomaや,high grade B-cell lymphoma with MYC/BCL2 translocationなどのaggressive B-cell lymphomaにおけるMYCのfusion,あるいはsplit FISH,免疫組織化学での評価が困難なfollicular lymphomaの場合の,BCL2のFISHがあります.また,PCRについては腫瘍量,検体の状態(凍結検体が入手可能かパラフィン検体のみか)を考慮して,サザンブロット法かPCR法かの選択を行う必要があります.NGSについてはがん遺伝子パネル検査がこれから導入されていきますが,リンパ腫診断においては亜型分類が不可能なものなどに限られると考えます.
2.白血病,MDSなどの疾患においては新鮮検体(末梢血あるいは骨髄穿刺液)を採取するのが第一選択になると思います.これに対し,リンパ腫の病理組織検体ではFFPETの検査が標準と考えます.ただし,RNAシークエンスによる融合遺伝子が知りたい場合においては,できるだけ凍結による新鮮検体が有利と考えます.日本血液学会「造血器腫瘍ゲノム検査ガイドライン」では,疾患・病期ごとにパネル検査の推奨度と遺伝子のエビデンスレベルを整理して公開されています.
3.これに関しては,基本的にREADシステムを取り扱っているLSIメディエンスに直接問い合わせてください.
4. READシステムにおいても,比較的高頻度にCTガイド下針生検材料が提出されてきますが,どの検査項目を目的にしているのかにより,必要な腫瘍量が変わってきます.腫瘍細胞が比較的よく含まれている(概ね30%以上)であれば,フローサイトメトリーでの解析も比較的やりやすいと考えます(基本的にフローサイトメトリーと病理組織を見れば,おおよその腫瘍量は判別がつきます).