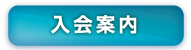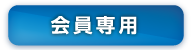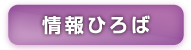病理組織検体を使用した遺伝子関連検査の精度向上―明日からできる効果的な方法―
【質問事項】1.EDTA中性脱灰液を用いた場合,脱灰時の温度(室温,37℃,高温)や期間(数日,1週間,1か月程度)によるDNA・RNAの品質への影響についてご教示ください.
2.セルブロック作製時に溶血剤を使用した場合,DNAやタンパク質の免疫染色への影響についてご教示ください.
3.当院では甲状腺オンコマインの陽性率が低いと感じています.甲状腺など実質臓器の固定において,注入固定を行うことで陽性率が向上する可能性についてご教示ください.
4.酸性脱灰をした組織をVIPで処理する際、遺伝子検査を行う検体との併用時の薬液交換について,必要な範囲(エタノール、キシレン)をご教示ください.
5.パラフィン切片を未染色標本として遺伝子検査に提出する場合,孵卵器に入れる時間や温度,乾燥状態との関係についてご教示ください.
6.脱灰したブロックと通常検体を同時にプロセッサーにかける際の注意点,薬液の取り扱いについてご教示ください.
7.薄切から伸展の方法についてお伺いします.切片を浮かべる際の水は蒸留水が望ましいか,伸展の温度・時間,切片乾燥時の適切な温度についてご教示ください.また,標本作製の具体的手順を記載した参考書籍があればご紹介ください.
8.精度管理について,当院では遺伝子検査を外注しており結果は紙媒体のため統計が取れません.貴施設では外注結果をエクセル等で蓄積し,データ管理をされていますか.実施されている場合,その具体的な方法についてご教示ください.
【回答】
1.硬組織を含む検体をゲノム検査,研究に供する可能性がある場合には,EDTAによる緩徐脱灰を行うことが推奨されています.脱灰前のホルマリン固定が長期の場合はDNAの断片化を認めます.EDTA使用時の温度や期間に関しては具体的に示されていません(ゲノム研究用病理組織取扱い規程第2版).
脱灰は,温度を上げると短時間で完了できるという利点がありますが,高温や長期処理は核酸・抗原性に悪影響を及ぼす可能性があります.遺伝子関連検査を優先する場合,「小切片化した上で,EDTAを用いて室温で十分に撹拌・頻回交換して最短で終える」ことを推奨します.腫瘍組織に柔らかい部分があれば,脱灰せずに標本を作製し,【ゲノム用FFPE】とすることを推奨します.
2.形態保持に有効な有機溶媒系溶血剤(例:メタノールやエタノールを主成分)を使用した場合,DNAの断片化の原因となり,特にNGSでlong-readや高カバレッジが必要な領域での解析には不利になります.RNAは化学的に変性しやすく,品質が著しく損なわれる(RIN値が低下)可能性があります.また,蛋白構造・抗原性への影響を受けやすいと言われており,膜抗原や一部のサイトプラズマ抗原は影響を受けやすく,染色性が低下する可能性があります.
3.一般的には,注入固定をすることは,陽性率向上の期待ができます.甲状腺癌においては比較的組織が小さいことが多く,注入固定を行わなくても良好な検査結果が得られています.もし,検査が成立しており,核酸の収量に問題がなく陽性率が極端に低い場合には,以下の点をご確認ください.
・組織の摘出から固定までの時間や操作内容(臨床側との連携が必要)
・病理での一連の操作手順の再確認
・石灰化を伴う組織の脱灰処理の影響
・腫瘍割合の確認
4.酸性脱灰液は,処理開始前に十分に中和処理を行い,残留する酸の除去後に処理を開始する必要があります.アルコール,キシレン系の溶媒に酸を持ち込むことによりpHが変化するために,核酸が影響を受けます.当院では,脱灰した組織は,1日かけ十分に中和処理を行っています.密閉式自動固定包埋装置での酸性脱灰後の組織処理は,1週間に1回に限定し,処理をした翌日に薬液交換を行っています.具体的には,アルコールは7槽中2槽の液を新しく入れ替え,タンクを繰り上げます.キシレンは3槽中2槽に液を新しく入れ替え,タンクを繰り上げます.洗浄用のアルコール,キシレンは全て交換しています.これは,脱灰組織の有無にかかわらず毎週1回行っています.
5.パラフィン切片を未染色標本として遺伝子関連検査に提出する場合,ふ卵器には入れないでください.理由は,溶けて固まったパラフィンで,スライドガラスの組織が認識しづらくなるからです.免疫染色の場合にも,陽性対照となる切片を載せづらくなります.スライドガラスは,室温にて水分を除去,自然乾燥を行います.乾燥を確認後に速やかにケースに入れて送付してください.
6.理想的には,性脱灰液を使用した場合,伝子検索用の組織と同時に密閉式自動固定包埋装置にかけることは推奨しません.詳細は4に記載.
7.核酸抽出を必要とする検査の場合
①水について
切片を浮かべる際の水はnuclease-free waterを使用している施設もありますが,水道水で問題ございません.
②伸展について
伸展は不要です(スライドガラスから組織を削り取って回収し,核酸を抽出するため).
③乾燥について
詳細は5に記載.
④参考書籍について
標本作製の具体的手順は,検査によって異なることがありますので,各検査会社が作成している標本作製マニ
ュアルなどもご使用ください.
インターネット上で公開されている指針,規程を3つ紹介いたします.
・日本病理学会・日本臨床検査医学会「がんゲノム検査全般に関する指針」
・一般社団法人日本病理学会「がんゲノム検査全般に関する指針」参考資料
・一般社団法人日本病理学会「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」
8.外注先から紙で返却される検査結果を,病理を担当する技師が確認してエクセルでデータ管理を行っています.具体的には,検査ごとの各遺伝子の陽性率を全て出せるようにしています.