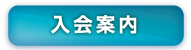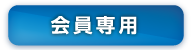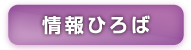HOME > 例会抄録 > 第112回日本病理組織技術学会 > 悪性リンパ腫の統合病理診断
悪性リンパ腫の統合病理診断
髙田 尚良
富山大学学術研究部医学系病態・病理学
リンパ腫は国立がんセンター2020年のがん統計予測において、全がん種中第7位の罹患数であり、年間人口10万人あたり約28.5人、白血病の約2.5倍の頻度とされ、血液腫瘍中で最も頻度の高い悪性腫瘍であるとされている。また、年齢調整罹患率も40年前と比較して約2倍の頻度増加があり、今後高齢化が進むにつれて増加する悪性腫瘍の一つであると考えられる。本邦においては地域差はあるものの、大まかな頻度してはB細胞リンパ腫が約80%、T細胞リンパ腫が約15%、ホジキンリンパ腫が約5%となっている。この中で日常で遭遇する頻度の高い亜型であるびまん性大細胞型B細胞リンパ腫、濾胞性リンパ腫、濾胞辺縁帯リンパ腫を併せると全リンパ腫のおよそ6割を占めていることがわかる。現行のWHO分類第5版においては、B細胞リンパ腫においては75の病型が、T/NK細胞リンパ腫においては32の病型が存在する。では、何故このような多数の病型に分類する必要性があるのか?それは病型ごとに難治性となる頻度が異なり、選択されるべき治療法が異なるからであると考えられる。また、病型ごとにおいてkeyとなる遺伝子異常が異なる。以上の観点からリンパ腫診療においてはまず詳細な病型分類が必要と考えられる。実際のリンパ腫病型分類においては、H&E染色による形態所見が最も重要であるが、それに加えて免疫組織化学、フローサイトメトリー、遺伝子再構成検査、FISHなどの結果を統合し、より精密な病型分類を行っている。本講演ではその統合診断の実際について具体的な症例も含めて述べる。