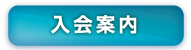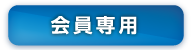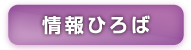HOME > 例会抄録 > 第112回日本病理組織技術学会 > Grocott染色の改良法 アンモニア銀を用いた真菌染色法について
アンモニア銀を用いた真菌染色法について
山田正人
社会福祉法人三井記念病院 臨床検査部 病理検査室
感染症は細菌、真菌、ウィルスなどにより引き起こされ、その同定や観察には染色法、培養、抗原、抗体検査、遺伝子的検査法などが用いられる。病理組織学的に真菌の証明にはPAS染色、Grocott染色、mucicarmine染色などが用いられる。しかし、組織中の真菌は種類や菌塊の大きさ、死滅した状態など多様性であることから染色法により差がある中で、Grocott染色は真菌の染色性に優れることから日常的に行われている。
今回、温故知新のテーマにGrocott染色を取り上げた。
Grocottのメセナミン銀法は1955年、GrocottがGomoriのグリコーゲンとムチンを目的としたメセナミン銀法を利用して組織内の真菌を染めるために単純化した方法である。酸化をクロム酸で行い、生じたアルデヒド基にメセナミン銀を反応させる方法である。輪郭が明瞭に褐色〜黒色に染色される真菌と背景染色にライトグリーンを用い、コントラスト良く観察することができる。しかし、粘液やグリコーゲン、リポフスチン、メラニン色素、石灰化物質、膠原線維、好銀線維なども染色されることから、ときに真菌の同定を困難にする場合がある。また、メセナミン銀液の反応は加温する必要があり、その方法にパラフィン溶融器や温浴槽が用いられる。反応時間においては一定ではなく顕微鏡で確認して終点を判断することから、染色者あるいは染色を行うたびに染色結果に差が生じる可能性がある。
1987年に當銘らは「アンモニア銀液を使用した再現性のよい組織内真菌染色法」―クロム酸アンモニア銀法―を報告している。酸化剤と時間はクロム酸60分で変更はないが、メセナミン銀液の代わりにアンモニア銀液を用いたことにより真菌の染色性を再現性がよく行うことができるとともに、膠原線維などの結合組織が陰性であると述べている。再現性については、メセナミン銀液と比較し、反応時間の許容範囲が広いことやアンモニア銀液の作製が簡便であること、染色性の強さを塩化金の時間で調整できることを挙げている。また、背景が共染しないことでHE染色をはじめ、膠原線維染色、弾性線維染色などと重染色が可能であったとされる。
発表ではクロム酸アンモニア銀法の紹介に、酸化剤とその時間による変化などを加え解説する。