
Fig. 1. Water Immersion Experiment
宇宙航空環境医学 Vol. 43, No. 3, 95-113, 2006
総説
日本における宇宙医学の歴史−宇宙開発事業団を中心として−
関口 千春
1東京慈恵会医科大学宇宙航空医学研究室
2宇宙航空研究開発機構
History of Space Medicine in Japan, Especially in the National Space Development Agency of Japan
Chiharu Sekiguchi
1Division of Aerospace Medicine, The Jikei University School of Medicine
2Japan Aerospace Exploration Agency
ABSTRACT
All space-medicine specialists recognize that Japanese space medicine does not have a long history, but few of them could explain clearly when and how Japanese space medicine started and developed. The author joined the Space Medicine Laboratory in the Jikei University School of Medicine, where Japanese space medicine research had just started, in the late 1960s. In the early 1980s, Japan was invited to participate in a space experiment conducted by a Japanese astronaut flying in space. Many medical researchers were interested in conducting actual space medicine experiments in the Space Shuttle, and several selected researchers actually conducted space medicine studies in space. The National Space Development Agency of Japan (NASDA) subsequently provided funds to support researchers in Japan. Moreover, NASDA began to engage in space medicine research and to conduct health care for Japanese astronauts. More detail will be provided in this review.
(Received: 4 September, 2006 Accepted: 11 September, 2006)
Key words: Space Medicine, NASDA, History
I. 宇宙医学研究活動
A. 黎明期 −慈恵医大における佐伯らの活動−
1966年に慈恵医大に宇宙医学研究室が創設され,その教授として佐伯が就任,その時から日本の宇宙医学研究の芽が出てきたといえる。当時旧ソ連とアメリカでは有人宇宙飛行競争の真っ只中,しかし日本はまだまだ宇宙に目を向ける余裕はなく,戦後の高度成長時代の始まりで,有人宇宙飛行は遠い別の国で起こっている夢のある出来事として横目で見ていた時代である。そんな中で佐伯が始めた宇宙医学研究では,実際の有人宇宙飛行研究に関与することは難しかったため,地上での模擬実験を中心として実施されていた。その典型例が微小重力状態を地上で模擬する方法として,首から上を出し身体全体を水に浸けるという水浸実験であった。一方,1968年に慈恵医大を卒業した関口は,学生時代から宇宙医学に興味を持ち,この宇宙医学研究室に出入りしていたが,医学部卒業後,インターン研修,そして医師国家試験を通過した後の1969年にはこの宇宙医学研究室に助手として入り研究をスタートさせた。
この水浸実験の最初の被験者が関口であり,当時の慈恵医大の地下に設置された暗い研究室の部屋で3日間水の中で生活したことは今でも鮮明に覚えている。最近ではヒトを被験者とした研究を実施する前には倫理委員会の審査があり,その審査を通過しなければ実験は許可されない。しかも実験の被験者に実験を企画した研究者の弟子がなることは倫理的立場から許されないことになっている。そのような被験者でなくとも実験参加に対する同意をとることは当然のことであるが,当時はそのようなシステムはなく,教授が被験者になって欲しいと言うのだからその助手が被験者になるのは当然という時代であった。現代ではそのようなことは考えられないことである。
最初の数時間で水浸による胸腔内の陰圧呼吸から生ずる体液シフトが起こり,その結果心容積の拡大からくるGauer反射が惹起され,尿量増加そして明らかな脱水が進行していった。最終的に3日目には血液の濃さを表すヘマトクリット(Ht)は58% まで上昇,自覚的にも倦怠感が強く,しかも水中での睡眠では,顔が水について溺れるのではないかという不安もあり,もちろん熟睡などできず睡眠不足と脱水で大変な思いをした。確かに水浸法による微小重力の模擬では,体液シフトがより顕著に起こってしまうことなどから種々問題はあるものの当時としては非常に画期的な研究であり,その成果は当時の国際学会で発表されており,日本に宇宙医学研究室ありと認識させるに十分であった。その後宇宙医学の研究は1980年代のスペースシャトルを利用した宇宙実験の可能性まで,佐伯の研究室において細々と続けられていた。図1は実際の関口を被験者とした実験ではないが,その後続けられていた基本的に同じ水浸実験の時のもので,水槽内を見ているのは当時のドイツ航空宇宙医学研究所の所長Dr. Kleinとその隣は現慈恵医大・宇宙航空医学研究室・助教授の須藤である。
 |
|
Fig. 1. Water Immersion Experiment |
B. 宇宙開発事業団を中心とした宇宙医学研究の始まり
1. 第1次材料実験計画への参加とライフサイエンス研究
スペースシャトルを利用した日本人宇宙飛行士による日本初の宇宙実験が第1次材料実験計画,通称FMPT(First Material Processing Test)計画であった。1981年にアメリカNASAは,スペースシャトルの初飛行を成功させ,それによってかなり大きな貨物を宇宙空間へ運べると同時に最大7名までの宇宙飛行士を最長約2週間,宇宙に滞在させることを可能にした。これを利用して宇宙実験,宇宙観測などが以前に比して飛躍的に多くできるようになり,日本にも宇宙実験に参加しないかとNASAから打診,その結果,宇宙開発事業団(NASDA)が日本人宇宙飛行士を選抜して彼らに宇宙空間での特徴を利用した実験を実施しようというのが,FMPT計画であった。FMPTの目的は宇宙環境の特殊性を利用した宇宙実験を行うことであったため,材料実験と生命科学実験の大きな2つの分野の実験を宇宙で実施することになった。これには公募で選定された12の生命科学と22の物質科学実験のテーマ,それに後述するが1つのL-0実験と呼ばれた宇宙飛行士の健康管理実験が含まれていた。一方では,これら実験を実施する日本人宇宙飛行士を選抜・訓練し,飛行させるというこれまでの日本では考えてもみなかったことを実施することになった。
関口がNASDAに入る前には,これらライフサイエンス実験の国内とNASAなどとの調整の要となっていたのが,2005年8月に他界した松宮であった。彼はもともと野村総合研究所の職員として彼のこれまでのライフサイエンス知識・技能や豊富な人脈を生かしてNASDAのFMPT計画の中の医学を含めたライフサイエンス実験をサポートしてきた。1985年に関口がNASDAに入ってからは医学に関しては関口が担当することになったが,当時まだ入ってまもない関口は,NASDAでのライフサイエンス実験の国内外での調整の仕方のノウハウを十分につかめず,彼とはいろいろと議論したことを覚えている。しかし,宇宙実験の進め方,NASAとの調整のノウハウなど彼から得るものは非常に大きく,その後のNASDAでの業務を進めていく上で非常に参考となった。そんなことから1985年以後は,医学を除いたライフサイエンスに関することは,松宮とそれにFMPTで宇宙飛行士に応募し,途中まで選考過程に残っていた長岡(現藤田保健衛生大学・教授)が引き継ぐことになり,健康管理と宇宙医学研究に関しては関口が担当することになった。
2. FMPTでのライフサイエンス実験,特に宇宙医学関連実験
最初に述べたように1960年代後半から1970年代の日本における宇宙医学研究は慈恵医大の佐伯のみが実施していたといっても過言ではないが,このFMPTにおいて12のライフサイエンス実験の中には以下の表に示すいくつかの医学関連研究テーマが含まれており,このFMPTを契機として日本における宇宙医学研究も少しずつ実施されるようになってきた。
以上のようにヒトを対象とした宇宙医学関連実験は3つあり,そのうち2つのヒトを対象とした研究(L-1, 4)と,それにコイを使った研究であったが宇宙酔いに焦点を当てた研究1つ(L-2)が名古屋大学・環境医学研究所からで,佐伯の地道な宇宙医学研究に加えて1980年代からは名大の環境医学研究所が宇宙医学研究の中心的役割を担うようになった。さらにその後は,後述するNASDAのフロンティア共同研究制度,そして公募地上研究制度が導入され,日本の多くの医学系,生命科学系の研究者が宇宙医学の研究を行うようになっていった。
| 番号 | 被験体 | 研究タイトル | PI | 研究機関 |
| L-0 | ヒト | 日本人宇宙飛行士の健康管理 | 関口千春 | NASDA |
| L-1 | ヒト尿 | 搭乗者の内分泌系の反応と代謝変化 | 妹尾久雄 | 名大・環研 |
| L-2 | コイ | 無重量順応過程における視−前庭性姿勢・運動制御の研究 | 森 滋夫 | 名大・環研 |
| L-4 | ヒト | 宇宙空間における視覚安定性に関する研究 | 古賀一男 | 名大・環研 |
| L-6A | 腎臓細胞 | 哺乳類培養細胞の超微細構造と機能に及ぼす無重力の影響に関する研究 | 佐藤温重 | 医科歯科大 |
| L-6B | ヒトリンパ球 | ヒト抗体産生細胞の細胞増殖と抗体産生に及ぼす無重力の影響 | 菅沼俊夫 | 三井製薬工業(株) |
| L-7 | ニワトリ受精卵 | 鶏胚の軟骨と骨の成長に及ぼす無重力の影響 | 須田立雄 | 昭和大歯 |
3. FMPTでの健康管理(L-0)実験
毛利,向井,土井の3名の宇宙飛行士の中から最初にスペースシャトルに搭乗する宇宙飛行士は毛利飛行士に決定し,地上での健康管理も順調に進んでいった。一方では健康管理のための医学データ取得は医学研究であり,宇宙飛行士の健康管理を行う医師であるフライトサージャン(FS)業務とは別々に実施すべきであるとの議論がでてきた。というのはL-0実験は健康管理という名がついてはいるものの,飛行士は実験の被験者であり,彼らにとって不利益になる可能性があるという考え方である。そのため健康管理は,関口の後にNASDAにFSとして入った弓倉が,医学データ取得のための実験は関口が行うという切り分けになった。FMPTの実験テーマは日本全国から公募で選定され当時の最新の研究テーマとして宇宙飛行の機会を待っていたが,関口の担当したL-0実験は後から健康管理のデータ取得ということで追加されたものであった。そのため公募で選定された生命科学実験はLife Scienceの頭文字をとってL-1, L-2, L-3などの略称番号がつけられたが,健康管理実験は公募で選定されたテーマでなかったこと,後から追加で入れられたということかL-0という略称がつけられた。内容は飛行中の心電図,呼吸,皮膚電気反射,血圧などの生体情報を取得しデータレコーダーへ記録,その一部をリアルタイムで地上に下ろし,宇宙飛行の身体への影響を調べようとするものであった。
内容自体は簡単な実験であったが,最初の日本人宇宙飛行士の宇宙飛行時のデータ取得ということと宇宙実験の特殊性から,機材への安全性要求が厳しく非常に大掛かりな実験となってしまった。今ならこのような生体情報を記録して地上にダウンリンクするのに小さな装置で済むのだが,当時の技術からかなり大きなものとなってしまい,毛利飛行士はランドルセルのようなBackpackを背負っての飛行となってしまった(Fig. 2)。いくら無重量状態で重さがないとはいえ,ある程度重量のあるものを背中に背負っているため体を回転させて方向を変えるときなど慣性力がかかり,ただでさえ無重量状態で自身の身体の制御がうまくいかないところにもってきてこのような余分なものを背負ったこと,飛行初期には慣れておらず,自分の身体の動きを思うようにできなかったとなどからこの装置については彼から非常に評判が悪かった。
実際の宇宙実験のデータ取得は,アラバマ州ハンツビルNASA・Marshall Space Flight Center (MSFC)内にあるPayload Operation Control Center (POCC)にすべて集められ,関口を中心としたL-0実験チームは機器を開発担当した日本光電の技術者,慈恵医大・耳鼻科の石井などからなっていたが,その他のライフサイエンス実験チームの人たちとともにPOCCに時々刻々と送られてくるデータをみて興奮したことを覚えている(Fig. 3)。
一方,宇宙飛行をしている宇宙飛行士たちは12時間交代の2チームに分かれて作業しており,実験自体は24時間常に行われるというスケジュールが組まれていた。毛利飛行士は飛行初期には現地時間の昼ごろから真夜中にかけて作業するチームであったため地上でデータをモニターするわれわれL-0実験チームも午前中から夜遅くまでのモニターとなったが,シャトル飛行士の1日は24時間でなく,少し短かったため毎日少しずつ前へずれていき,最後は明け方から夕方までの勤務となった。飛行中実験機器の水漏れトラブルなどいくつかの問題点を克服して約1週間の飛行は,着陸地点の天候不良により予定より1日延長されて8日間となった。関口は飛行直後の毛利飛行士の健康管理データ取得のため飛行終了直前の前日にはMSFCからフロリダ州にあるKennedy Space Center(KSC)に移動となった。
着陸前日にはKSCに行くため飛行機を乗り継ぎ,フロリダ州のオランド空港からはレンタカーでKSCに直接行き,その日のうちに翌日のKSCへの入門許可証を入手した。翌日のシャトル着陸に備えてKSCに入るのは非常に早朝となるため,前日に入門許可証を取得しておいた方が無難だったからである。着陸日には,朝9時ごろの着陸予定に会わせるためその前にKSCの医療施設に着いていなくてはならず,早朝5時ごろにはホテルを出てKSCに向かい,現地には6時前には到着して待機となった。しかし,KSC周辺の天候不良のため毛利飛行士の乗ったシャトルはもう1周地球を回り,予定より1時間半遅れた午前10時半頃にKSCの滑走路に無事に着陸した。それから実際に毛利飛行士が,データ取得をする場所に到着するまでにはシャトルの安全確認,着陸直後の健康診断,そして着陸地でのセレモニーなど種々の過程があり,かなりの時間待った。そんなことで実際に毛利飛行士らのシャトルクルーが医療施設に到着したのは着陸後2時間以上経過した昼過ぎであったと記憶している。それからは着陸直後の健康診断,L-0実験を含む各種の飛行後のデータ取りと分刻みで毛利飛行士のスケジュールは進み,それらすべてが終わったのは毛利飛行士が医療施設についてから2時間以上経っていた。8日間の宇宙飛行を終えて帰還した毛利飛行士はただでさえ疲れているところに飛行後もデータ取得のスケジュールが一杯でさぞかし疲れたことだろう。
このようにして取得した心電図,血圧などのデータは飛行後,数人の研究者により解析され,宇宙医学関係の学会で発表されたが,ここにその一部を紹介する。飛行初期の心拍数及びGraybielの動揺病スコアーはやや高値を示し,その後徐々に適応する過程が見られたが,飛行士のパフォーマンスに影響することなく経過した。また飛行前後に実施された起立試験では,心拍数の増加が飛行前に比して大きく,循環器系は宇宙飛行によって軽度の影響を受けたと考えられた。その他血圧,Htなど飛行士の健康に大きく影響した所見を認めなかった1)。以上のデータはその後の宇宙飛行士の健康管理データベースになり,さらにその運用方法などは初めての経験として種々の学ぶところもあり,その後のNASDAの宇宙飛行士健康管理運用に生かされている。一方,ヒトを利用した宇宙実験計画書をNASAの要求に従って英語で作成し,しかもこの計画書をNASAの倫理委員会に提出する作業とその倫理委員会でのやりとり,そして実際のヒトを利用した宇宙実験の具体的方法などは,その後の NASDAでの同様の宇宙実験の準備や実施に大いに参考となった。
 |
 |
| Fig. 2. Astronaut Mohri handling the experiment wearing a bulky backpack | Fig. 3. L-0 team is looking at data sent from Space Shuttle |
NASAは宇宙開発による成果を一般の社会生活などに還元するスピンオフを数多く出しているが,日本ではまだそれほど多くない。そんな中でこのFMPTのL-0実験で開発されたスピンオフとして挙げられるものに,日本光電の開発した電極と赤外線データ転送システムがあった。L-0実験では心電図や呼吸などを取得するための電極は長時間皮膚に添付しておかなければならず,これまでの電極をそのまま使用したのではかぶれたりすることがあった。このL-0実験では,24時間貼っておいてもかぶれにくい電極を開発,その経験を生かして現在では日常臨床で広く用いられている24時間ホルター心電図電極に使われている。また,宇宙船内において被験者の生体情報を集積・記録したバックパックからのデータを船内の機器に転送する際,ケーブルで接続されていたのでは被験者の動きが制限されてしまうこと,一方,ケーブルを使わないで通常の電波を使ったのでは他の電送システムと干渉することなどから赤外線によるデータ転送システムが採用された。このシステムも近距離のデータ伝送システムとして最近では良く使われているものである。
4. 地上基礎実験及び基礎データ取得
後述する宇宙飛行士の健康管理という実際の運用医学もNASAのお手本を元に着々と技術を取得していく一方で,健康管理に必要な宇宙医学研究も,テーマは限られていたもののNASDA内で同時に進行していった。最初は宇宙飛行士の医学基礎データ取得という名目で半年に一度宇宙飛行士の健康診断を行い,そのデータ分析,さらに軌道上で問題となる循環器系の研究や前庭系の研究などを非常勤の医師などの支援を得ながら開始した。本質的には先に述べた関口が中心となって進めていた宇宙飛行士の健康管理実験という通称L-0実験の地上での基礎データ取得(Fig. 4)ということで開始され,循環器系の研究は,日本大学医学部・衛生学教室・教授の谷島と同教室・助教授の宮本を中心としたグループとの共同研究を,前庭系の研究は慈恵医大・耳鼻科の石井を中心とした共同研究として実施された。これらを実施するにあたっては先にもあげたようにPS脚注1 棟と呼ばれる健康管理施設に設置された下半身陰圧実験装置(LBNP)は循環器系の研究に,前庭系の研究には回転椅子装置,直線加速度装置(Fig. 5)などが当初使用され,その後前庭系の装置としては振り子様傾斜装置を開発・使用,さらにアメリカから購入したEqui testなども追加された。これらの研究は毛利飛行士の飛行した1992年まで継続され,L-0実験の地上基礎データとして分析され,いくつかの論文として宇宙医学関連の学会で発表された。
|
|||
 |
 Fig. 5. Astronaut Doi on a Sled |
||
| Fig. 4. Yumikura(front)and Sekiguchi(back)are conducting the LBNP Experiment | |||
一方,L-0実験の基礎データを取得するためつくばでの地上基礎データの取得だけでなく,実際の宇宙実験で使用する器材を用いて短時間であるが無重量状態を作り出すことのできるKC-135での実験も行なった(Fig. 6)。20-25秒間という短時間の無重量状態の間に,毛利飛行士ら3名の宇宙飛行士の心電図,呼吸,眼振,血圧などをBackpackに記録,さらに被験者の頭部を前後左右に振った時の同様の生体情報の記録を行った。一方,これらにより,FMPTのL-0実験の基礎データを取得することができただけでなく,我々NASDAのFSも初めて短時間ではあるが無重量状態という貴重な体験をすることができた。
 |
Fig. 6. L-0 team conducting baseline data collection experiment in a 0-G airplane(KC-135) |
C. 日本人宇宙飛行士を対象とした飛行前後の筋骨格系実験(DSO-206)
FMPTでの健康管理実験の後を受け,さらなる宇宙飛行士の健康管理基礎データを取得するため,NASAの同様のシャトル飛行時に実施されていたDSO(Detailed Supplemental Objective)を参考に企画されたのが筋骨格系に焦点を当てた宇宙飛行前後の基礎データ取得実験であった。これは当時NASAが行なっていた種々の宇宙医学DSO実験の中に筋骨格系の実験がなかったことに関口が目をつけて,短期飛行でも何らかの成果があがるのではないかと考え開始したのであった。最初に行なわれたのは日本人宇宙飛行士として二回目に飛行した向井飛行士を被験者とした研究であり,日本大学の宮本が主任研究者として実験は実施された。宇宙飛行では筋の萎縮と骨量減少が起こることは知られており,短期間の飛行でもそれがどの程度なのかを知るため,筋肉は主に下肢筋の断面積を飛行前後にMRIによって計測し比較検討するもので,骨はDXAを用いてやはり飛行前後のデータを比較するというものであった。具体的には飛行前には数回にわたってコントロールデータをとり,飛行後では直後から3日後,1週間後,2週間,3ヶ月,半年とデータをとり,それらが飛行前のコントロールデータからどのように変化するかを観察した。第2回目の若田飛行士の飛行時からはNASDAにも研究担当医師の大島がプロパーとして入ってきたため彼にこの研究を任せ,これまでのMRIとDXAの変化に追加して血液・尿の骨代謝マーカーのデータも収集するようになった。驚いたことにわずか2週間の飛行でも筋肉は部位によっては約15% も減少することがわかったが2),骨量に関しては有意な変化は見られなかった3)。その後スペースシャトルに日本人が飛行する際,少なくとも野口宇宙飛行士の飛行までは毎回この研究は実施されており,筋骨格系の貴重なデータベースとなっている。
D. ロシアでの国際閉鎖実験
国際宇宙ステーション計画を控え,日本人宇宙飛行士の長期宇宙滞在での精神心理的問題は重要な課題としてクローズアップされてきた。特に日本人は異文化という観点からもこの問題は避けて通れず,ISS滞在までにその問題点の洗い出しを行い,その対策を立てておかなければならないということから,閉鎖環境実験についてロシア保健省の生物医学問題研究所(IBMP)と共同研究を実施することになった。この研究にはNASDAだけでなく,カナダ宇宙庁(CSA)とヨーロッパ宇宙機関(ESA)も参加して大掛かりな共同研究となり,実際にはモスクワにあるIBMPの施設において1999年7月から2000年4月にかけて実施された。実験に使用したIBMPの施設は,もともと火星飛行の模擬実験に使用するために1960年代に作製されたものと聞き,Fig. 7に示すようないくつかのモジュールからなっていた。実験に参加した被験者は長期滞在を行った3群(第1〜3群: 各4名)及び短期滞在(5日〜3週間)を行った4群の計7群で構成された。被験者滞在スケジュールはFig. 8に示すように,8ヶ月間滞在するロシア人グループ4名の被験者に,各4人で構成される3つのグループの被験者群が3ヶ月間1グループずつ滞在するという基本的パターンに短期滞在グループが時々訪問するというパターンで行なわれた。8ヶ月間滞在するグループ以外はカナダ人,ドイツ人,オーストリア人,それに日本人などのいろいろな国からの被験者が入っており,モジュールの中で共同生活を行い,その間に種々の精神心理のテーマを主体とした実験を行なった。この詳細は平成14年7月に作成された宇宙開発事業団技術報告書4,5) に記載されているのでそれを参照していただきたいが,その中で起こったいわゆるセクハラ事件などにまつわるNASDAやIBMPの対応などについて簡単にここで触れる。
 |
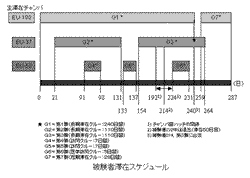 |
| Fig. 7. Isolation Chamber Module in Russia | Fig. 8. Experimental Schedule |
事件は現地時間12月31日の大晦日の夜に発生,中に入っている被験者は1月1日の前夜祭ということで,なぜか中にはウオッカ,ワインなどが持ち込まれてパーティーとなった。そんな中でロシア人被験者の一人がカナダ人女性被験者に対してセクハラ,また同じ時にロシア人被験者同士で殴り合いの喧嘩が発生した。事の次第は,グループリーダーのオーストリア人被験者(当時のNASDA招聘研究員ノルベルト・クラフト)の発信したメールを時差の関係もあり正月2日の朝に関口が読み判明することとなった。びっくりしたが時差の関係からすぐに対処できず,同日のロシアの夜が明けるのを待ち,日本時間の午後に現地に連絡,しかし,実験を現場で管理しているIBMPのスタッフやNASDAからの委託で実験をサポートし状況をモニターしていた有人宇宙システムの人はまったく知らず,それから大問題となった。その後,関口の正月休暇は吹っ飛んでしまい朝から晩までその調整が続いたが,何せ時差が5時間,ロシア人との通訳を入れての電話会議ではことの状況も十分につかめず,一方では中に入っている被験者たち特に被害者側であると自称するオーストリア人をリーダーとする日本人・カナダ人を含むグループからの苛立ちなどがあるため,日本側実験責任者である関口は厳寒のモスクワに行っての調整・交渉となった。約1週間の滞在中,ほとんど毎日IBMPの研究所においてIBMPとCSAの関係者らと夜10-11時と遅くまで会議を持ち,ホテルに帰ったのは夜中の12時過ぎることも多々あった。結局は残念なことに日本人のみが閉鎖の実験のチャンバーから出ることになってしまい実験は失敗したかのようにみえたが,むしろいろいろな面で閉鎖実験の貴重な成果が得られた。すなわち,将来の宇宙ステーションでの精神心理の問題点をある程度洗い出すことができ,さらにそれらの教訓から対策法作成の示唆が得られたことは大きな成果であった。当時招聘研究員としてNASDAに所属しチャンバーに被験者として入っていたオーストリア人研究者ノルベルト・クラフトと精神心理担当の井上などが,多くの研究テーマを実施したが,その研究テーマの結果詳細については報告書を,またこの事件の教訓に関しても,専門の委員によって議論し,その結果の詳細も報告書としてまとめられているので参照していただきたい。一方では,これらの問題をともに苦労して対処してきたIBMPの研究者らともより親密な関係を築くことができたことも大きな成果であった。Fig. 9は実験終了直後に閉鎖チャンバーから出てきて記念撮影された被験者の写真を示す。
 |
| Fig.▽9. Subjects just after 3 months stay in the chamber |
E. フランスでの長期ベッドレスト実験
長期宇宙滞在での大きな生理学的問題として骨量減少や尿路結石発生のリスク増大があることはよく言われている。これらの対策法として現在,宇宙滞在中の運動療法が用いられているが,十分なものとなっていない。高齢者に生ずる骨粗鬆症の治療薬として最近用いられている骨吸収抑制剤であるBisphosphonateをその対策法として用いてはどうかという発想でNASDAが実施したのがフランスでのベッドレスト実験であった。フランスの宇宙機関CNESに所属し,Toulouse市にある宇宙医学研究所MEDESから3ヶ月間のベッドレスト実験に参加しないかという誘いがあり,NASDAは上記趣旨を主要テーマに共同実験として参加することになった。本研究実施に当たっては研究主任責任者を大島として実施,常時現地に滞在して実験を行うには人員が足りないこと,予算的にも限られていることなどから現地のフランス人研究者にある程度委託して行い,大島が頻回にフランスに赴いて実験データの取得を行うという方法で行った。
 |
 |
| Fig. 10. Logo of Bed-rest Experiment | Fig. 11. Subject lying on the head down bed |
実際のBed rest実験は2001年から2002年にかけて施設の被験者収容人数の関係から2回に分けて行なわれ,被験者はそれぞれ3つのグループ,すなわち1つは対象群で何もしないグループ,2つ目はフライホイールによる運動負荷群,そして3つ目のグループはBisphosphonateを使用した薬剤群であった。実験中,ロシアで発生したような大きな問題点はなかったが,すべての日本側実験のデータ取得も現地のMEDESの研究者に任せたため,あるデータでは信憑性に欠けるものもあった。予算の都合上人員を派遣できなかったためであったが,やはり実験は研究者自らが直接実施すべきであるという大きな反省点となった。ただ実験の所期の目的であったBisphosphonateの効果は仮説通りで骨量減少の予防と尿路結石発症のリスクの低減を示した6)。本実験はその後のISSを利用した宇宙実験のBisphosphonateの効果の飛行検証実験に至っている。
F. フロンティア共同研究制度
後述するが1988年から1990年前半には宇宙医学研究の現状を調査するため,日本の各分野の専門家に宇宙医学研究における世界の現状の成果報告書を三菱総合研究所を通して作成した。この時に依頼した委員は,それまで宇宙医学の専門家ではなく,各専門分野の,例えば循環器系の専門家とか,筋肉の専門家であった。しかしこれらをまとめることでその時の宇宙医学の問題点を理解していただいたこと,一方ではその分野の日本のトップクラスの研究者であったことなどから,これらの研究者に対して助成金を交付することになった。本質的には宇宙ステーションでの微小重力実験に反映させることと有効な宇宙環境利用活動の発展に寄与することを期待してこの制度が発足した。これがNASDAから委託され宇宙環境利用推進センター(JSUP)を通して実施された「フロンティア共同研究」の助成金制度で,ライフサイエンスでは1995年から1997年までの3年間実施された。また,これはこれまでNASDAで実施してきた循環器系の研究と前庭系の研究以外にも宇宙医学研究を日本において推進する突破口を開こうという意味からも重要であった。この立ち上げにあたっては後述するが,厚生省より出向した医官である加藤が中心となって努力した。有人宇宙技術研究分野として,宇宙生物医学研究,心循環器系,骨・Ca代謝,筋肉系,神経・前庭系,栄養代謝,閉鎖異文化,そして物質循環技術などに分かれて研究助成金が与えられ総合的な宇宙医学研究が日本の各分野のトップクラスの研究者で開始された。
 |
| Fig. 12. LBNP Device |
このフロンティアの制度で研究助成金を手にした研究者らは自分らの研究室で宇宙医学に関連した研究を行なう研究者が多かったが,一方では先にあげたつくば宇宙センターに設置されたLBNP装置, 6°Head Down Bed,前庭系の各種装置などを利用して行なう研究者もおり,これらの装置はその後の公募の制度でも活用されてきた。
しかし,この制度は以下の理由から3年間という非常に短い期間で終了してしまった。すなわち,研究を希望した研究者を公募で募ったのでなく,以前に行った宇宙医学の調査研究で依頼した研究者に直接研究資金が渡ったため助成金の対象外の研究者から公平な制度ではないとの意見があったことなどからであった。そのようなことから次の公募研究システムにこれは引き継がれることになったが,日本のトップクラスの医学研究者に宇宙医学の問題点をある程度理解していただいたという点ではその功績は大きい。
G. 公募地上研究制度および国際公募制度
上記にあげたフロンティア共同研究システムに引き続き1997年から立ち上げられたのが公募による助成金制度であった。本システムは,日本の宇宙ステーションモジュール「きぼう」を中心とした宇宙環境を利用する準備段階として,幅広い分野の研究者に研究機会を提供し,宇宙環境利用に関連する地上研究を推進することを目的として創られた。また,宇宙環境で得られた成果を活かして科学・技術をより一層進歩させ,地上の生活や産業に役立てていくことが可能であるとしている。これまでに選定された宇宙医学に関連したテーマとしては,宇宙という閉鎖環境での睡眠・生体リズムの研究,微小重力下での骨量減少のメカニズムと予防・治療法に関する研究,筋萎縮に関する研究,そして宇宙酔いに焦点を当てた前庭系の研究など,宇宙医学で問題となる研究テーマに助成金が交付されてきた。一方,これと並んで実際の宇宙実験実施テーマを対象として国際公募の制度もあり,NASA, ESA, CSA, NASDAなどの国際宇宙機関が主体となって結成されている国際ライフサイエンスワーキンググループ(ISLSWG)が最終的な選定を行い,これまでスペースシャトルなどを利用した実験として日本人研究者のテーマもいくつか採択されてきている。
これらの制度を使って日本の医学やライフサイエンスの研究者らは,自らの分野の研究テーマの助成金を得るため応募し,公平な選考過程を通して研究費を獲得していった。選考委員会にはJAXAの宇宙医学担当として関口はその都度出席し,当初,委員も宇宙医学の問題点を十分に理解して頂いていない方もおり,こちらから宇宙医学の問題点を説明しつつ選考が行われていった。また応募テーマの中には宇宙環境を利用した研究という大義名分はあるものの,その本来の意味から多少外れ,自分の研究分野の研究を推進するため,宇宙との直接的な関係が不明確な研究も見られた。ある意味では,宇宙医学を研究者に広く知ってもらうためにはやむをえないことであったかもしれないが,最近では選考する委員も宇宙医学の問題点を熟知するようになり,その点は改善されてきているようである。
II. 宇宙医学運用
A. 日本初の宇宙飛行士の選抜
ここからは宇宙医学の運用,すなわち宇宙飛行士の健康管理がどのようにNASDAの中で展開・拡大して行ったかについて触れよう。NASDAにおける宇宙飛行士の健康管理に代表される宇宙医学運用が開始されるきっかけとなったのは,日本人初の宇宙飛行士を募集するというニュースが新聞などニュースメディアに出された1982年の2年ほど前の1980年頃,NASAの宇宙飛行士の医学基準に沿った選抜医学検査の検討が行われた頃からと思われる。すなわち,当時の東大の医用電子研究室・教授の大島正光を委員長としたNASDA・スペースシャトル利用委員会において,NASAの宇宙飛行士の医学基準とその選抜法が検討されたのであった。しかし,実際の宇宙飛行士の医学選抜は1983年から実施され,最終的に最初の3名が選抜されたのは1985年であるため,そのあたりが宇宙医学運用の始まりと言った方がいいのであろう。まず,日本人宇宙飛行士をNASDAで抱えるとなると彼らを健康管理する専属の医師が必要となり,その人をどのようにしてNASDAで確保するかが1つの問題となったようである。関口は1982年から1984年までの2年間,アメリカ,オハイオ州ライト州立大学の航空宇宙医学・修士課程に留学しており,その間にアメリカの当時の航空宇宙産業の大手会社であるGEの人から日本で宇宙飛行士の健康管理をするフライトサージャン(FS)脚注2 を探しているが,あなたはどう思っているかと聞かれたことを鮮明に覚えている。もちろん,航空宇宙医学は私のまさにライフワークであり,日本に帰ってからでも間に合うのなら是非やってみたいと答えたのであった。その後1984年に航空宇宙医学の修士課程を修了して日本に戻ると早速NASDAからそのような誘いの話があった。しかし当時の所属はまだ航空自衛隊の航空医学実験隊であり,留学から帰国したばかりのためすぐに退職するわけにいかず,当時の医学実験隊司令・黒田に相談,その結果,1年間の猶予後にNASDAへ転職してはどうかとの内諾を得た。一方,NASDAとしては宇宙飛行士の選抜をそれまで待つわけには行かず,その間にも事業団の中で宇宙飛行士の選抜,そして宇宙実験の候補選びは進んでおり,特に医学選抜は日本大学医学部の谷島を中心として行われていた。当時,宇宙飛行士の選抜は日本にとっても初めての経験であり,その基準はNASAの基準に則っていたものの,それら基準を満足するための効率的な評価検査法はどのようにすべきか暗中模索という感じで行われていたと言うのが実際のようであった。
|
|
|
| 脚注2: | フライトサージャン(FS)とは一般に軍のパイロットやNASAの宇宙飛行士を健康管理する専門医をいい,NASDAにおいても関口の入った当時から通称FSと呼んだ。2003年からはJAXAにおいてもFSが正式に認定されるようになっている |
約1年経った1985年の4月には関口はようやく航空医学実験隊を離れてNASDAに移り宇宙飛行士の選抜の真っ只中に入っていった。その時既に宇宙飛行士の選抜は,最終段階に入っていたが,選抜医学検査は,NASAの医学基準を満足するための最大限の検査項目からなっており,結果的に非常に多くの医学検査となった。具体的にはNASAにおいて宇宙飛行士の医学選抜で実施されていた検査以上の非常に細かい数多くの検査からなっており,宇宙飛行士の応募者たちは病院に約1週間入院して詳細に調べられた。そんな厳しい検査を受けて残ったのは12名で,さらにこの12名に筑波宇宙センターでの回転椅子や下半身陰圧試験などの特殊な医学検査や心理面接などを実施したのが,関口がNASDAに入る直前の1985年の冬であった。ここで選ばれた7名の最終候補者達をNASAのジョンソン宇宙センターでの医学検査を受けさせるために同行し,NASAのFSとこれら候補者を医学評価することが1985年4月に入った関口の最初の大きな仕事となった。
NASAの選抜医学検査は4日間ほどであったが,日本で行われた検査よりかなり簡略化されており,さすがに選抜医学基準を評価するためにあれだけでいいというのはこれまでのNASAの経験から得た結果なのであろうと感心した。蛇足であるが,その後の日本での選抜および日常の健康管理のための医学検査項目もこれらを参考にかなり簡略化したものとなっていった。話を元に戻して,NASAでの医学検査結果を踏まえて,その7名の候補者の中から毛利,向井,土井の日本人初の3名の宇宙飛行士が選ばれたのであった。彼らはその後,準備期間を置いて関口より約半年遅れてその年の11月にNASDA職員となったが,以後彼らの日常の健康管理,そして実際の宇宙飛行に関連した健康管理の実施は,関口およびそれに次いで入ってきたFSたちのもっとも主要な仕事となった。不慣れな文書作成などの業務を見よう見真似で行い,宇宙飛行士の健康管理計画書を作成,それに則って彼らの健康管理を実施していったが,何せ初めての経験であり,NASAでこれまでやられてきた方法を横目で睨みつつ健康管理を行っていったというのが本音であった。
第2回目の若田宇宙飛行士の選抜を中心にもう少し詳細に宇宙飛行士の医学選抜段階についてここで述べる。選抜に用いられた医学基準はNASAのミッションスペシャリスト(MS)の医学基準を適用して評価を行なったが実際の選抜は下の表に見られるように最初の書類審査に始まり,第1次,第2次,最終の第3次選抜試験と段階的に進められていった。1991年の夏にMS募集の正式発表がNASDAからあり,これを受けて8月末の締切までに372名の応募があった。書類選考は応募条件に合わない人のチェックであり,主な選考は診断書による血圧,身長,視力などの簡単な医学的な書類審査であった。書類審査を通った人は233名となり,彼らには第1次試験である英語,基礎的専門試験,簡易医学心理学検査などの筆記試験を中心に行なわれた。これを通過したのは53名であり,その中から45名が医学検査を中心とした第2次選抜試験を受験した。各候補者は詳細な医学心理学検査を受けるため,5日間都内の2つの大学病院に別れて入院,半分は日本大学板橋病院,残り半分は慈恵医大病院に入院して検査を受けた。
具体的にはMS医学基準に則った非常に詳細な医学検査を実施したが,各大学病院とも入院ベッドの確保や検査のスケジュール調整に大変苦労したことを記憶している。一方,各候補者は5日間入院して早朝から夜遅くまで集中的に医学・心理学検査を受け,候補者も精神的・身体的に大変だったと思われる。その結果,6名が合格となり,筑波宇宙センターでの最終の第3次選抜試験に進んだ。そこでは下半身陰圧負荷,回転椅子試験などを実施したが,これらの検査は我々FSが中心になり,非常勤の専門医師の協力の下に実施した。この検査の後,これら6名はFSの弓倉とともにNASAジョンソン宇宙センターに行き,4日間にわたる再び詳細な医学検査の受験となった。そして日本に帰国して最終的にNASDAの理事による面接を受け,これらの結果を総合して若田飛行士がMSとして選抜されたのであった。Fig. 13は選抜医学検査の1つである体力測定検査を,Fig. 14は選抜医学検査・精神科面接で2名の精神科医による構造化面接の実施風景を示す。
| 書類審査 | 372名 | 応募書類,健康診断書など |
| 第一次選抜 | 233名 | 簡易医学心理学検査,筆記試験(英語,教養) |
| 第二次選抜 | 53名 | 詳細な医学心理学検査,面接(一般,英語) |
| 第三次選抜 | 6名 | 特殊な医学検査,及びNASAでの医学検査,面接など |
 |
 |
| Fig. 14. Structured Interview by two psychiatrists | |
| Fig. 13. Physical fitness capability test among selection medical examinations |
第2次選抜時の45名の候補者についてどのような不合格疾患があったかについて簡単に振り返ってみる。医学的に失格となった候補者は,30名で 66.7%,この中で視力不足など眼科的理由によるものがもっとも多く35.6% を占め,次いで脳波異常,消化器疾患,循環器疾患の順となった。NASAの報告でも最も多い不適格理由は視力であり,次いで精神科,心循環器の問題であり,視力に関しては我々と同じ結果となったが,我々の結果では脳波異常や消化器疾患が上位を占めており,多少異なったものとなった。脳波の判定は多少主観的な要素もあり,今回は宇宙飛行士の選抜ということで境界領域と思われるものも厳しく判定したこともその理由の一つではないかと考えられた。また消化器疾患が多く見られたことは,NASAでは行わない上部消化管内視鏡検査の導入により,より客観的に上部消化管を検査できたことと,さらに日本人の本疾患の有病率の高さを反映した結果とも考えられた7)。
B. 健康管理と初期の健康管理体制
宇宙飛行士の健康管理をするにあたって,最初,どのくらいの頻度でどのような医学検査を実施して日常の健康管理を行ったらいいのかといった詳細な情報はなく,民間や自衛隊のパイロットの健康管理方法とNASAの方法をお手本に実施していくこととした。その結果,日本として始めての宇宙飛行士の健康管理のデータを保存しておくことも考えて,できるだけ頻回に実施し,病的な状態をいち早く察知しようと意気込み,項目によっては3ヶ月に一度,一般的には半年に一度といった通常のパイロット以上の厳密さで健康管理の医学検査を組んでいった。またこれらのデータは宇宙飛行士の基礎データを取っておくという意味合いも兼ねており,当時筑波宇宙センターの管理棟の裏にできたいわゆる宇宙飛行士の健康管理のための部屋であるPS棟といわれるところで行われた。検査項目は一般的な医学検査項目の他に基礎データとして前庭系の回転椅子や直線加速度検査,下半身陰圧検査(Fig. 15),トレッドミル検査による心肺機能検査,さらには心理面接なども入っていた。
このような頻回の検査の意図は,早期発見,早期対処のつもりであったが,飛行士側からはそれはむしろ身体の荒捜しをしているかのように取られてしまい評判のよくないものとなってしまった。そんな反省もあり健康管理のための医学検査項目やその頻度は徐々に減らし,数年後には現在とほぼ同じ1年に1回の医学検査となった。最近では健康管理のための医学検査項目,頻度などはアメリカ,ロシア,カナダ,ヨーロッパ,日本の医学関係者が合意した必要最小限のものからなっている。但し,日本独自の疾患特性を考慮して追加されている項目もあり,例えば,上部消化管内視鏡検査などはその例である。
一方,健康管理をするNASDA内の医学体制も徐々に整備されていった。先にも述べたように最初は宇宙飛行士のNASDA採用を行う前にその健康管理を行う専門医1名を1985年4月に採用,後に初代の宇宙医学研究開発室の室長となった関口である。その関口を事務的にサポートする人として3名が充てられ,現在広報部長である矢代,宇宙環境利用プログラム推進室・課長の上垣内,SEDから出向してきた松尾の3名であった。1985年当時,右に示す宇宙実験グループという18名の組織の下に第1次材料実験推進室があり,そこに関口以下4名のNASDA職員が宇宙飛行士の健康管理をする小さなグループとして任命されていた(Fig. 16)。但し,我々FSをサポートする医師として当時の日本大学医学部衛生学教室・教授の谷島と同教室・助教授の宮本,それに同大学内科の弓倉らがサポート要員として健康管理の医学検査時などの際に協力した。
 |
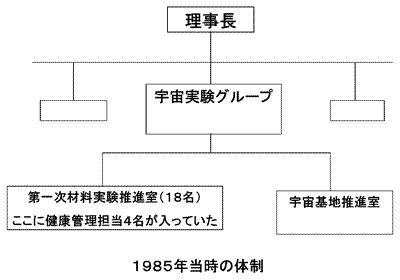 |
| Fig. 15. FS and engineers are conducting LBNP test to an astronaut at the PS examination facility | |
|
|
その後1988年には宇宙ステーション開発本部が設置され,健康管理グループはまだ宇宙環境利用グループの中の一集団に過ぎない存在であったが,その後9年たった1997年にはNASDA内に宇宙医学研究開発室が,主任医長以下7名の人員体制で組織上認められた。また1988年当時に戻るが,将来のNASDAの医学体制の充実を図るため常勤医師の公募が行われ,その結果,それまで非常勤で協力していた弓倉が採用された。彼の専門は循環器内科であったが,宇宙医学の専門家としての知識を習得するため,その年の7月から関口と同じアメリカ・オハイオ州デイトン市にあるライト州立大学の航空宇宙医学のResidencyに2年間留学した。その後も2〜3年おきにFSの採用が公募によって行なわれ,90年には村井が,93年には嶋田がそれぞれ採用された。採用直後より,同じコースにて約二年間航空宇宙医学の勉強をして帰国後に飛行士の健康管理を担当するFSとして勤務するようになりその数は1996年の時点で3名となった。その後もFSの採用は引き続き行われ,すべて採用したFSが在職していればかなりの数になったはずであったが,採用後短期間で辞職したものもいたため2002年関口が定年退職する時点で4名のFSであった。これは,当初宇宙医学という表面的には華やかな分野に見えて応募してくる医師も,実際の業務と想像していた業務のギャップ,医師としての待遇面での問題,さらにはその人の性格など医師採用の難しさと反省点を示しており,今後の1つの大きな問題であった。
一方では宇宙飛行士の健康管理を行っていくためには医師だけでなく看護師,しかも宇宙飛行士の健康管理を行なういわゆるフライトナースが必要であった。そのため元慈恵医大病院の看護師であった武井をAESからの常勤の契約職員として89年4月から採用した。彼女は非常に優秀な看護師で我々FSの手足となり,さらに宇宙飛行士とFSの間のバッファーとなったりし,なくてはならない存在となった。しかし,彼女は初代のNASDAフライトナースとなったのだが,残念ながら若くして病に倒れ92年の春には仕事半ばで辞職,その翌年の93年1月には他界してしまった。その後も近隣のつくばメディカルセンターなどから看護師が2-3年毎に交代してFSをサポートし,今日に至っている。
さらに健康管理業務を国の厚生業務の面から支援するため,関口が採用されて1年ほどしてから約2年交替で厚生省から医系の技官が出向して来た。彼らはいわゆる組織内での医学的なマネージメントを中心に実施,すなわち,宇宙飛行士の健康管理に必要な宇宙医学研究を体系的に行なっていくための検討を外部委員会に委託して進めたり,NASDA内での健康管理業務の具体的方法などを関口とともに上層部に説明するなどの業務を担当した。この厚生労働省からの医官の出向は現在も続いており,JAXA内での宇宙飛行士の健康管理業務内の重要な位置づけとなっている。厚生省からの初期の出向医官の貢献についてはもう少し詳細に次のセクションで述べる。
2005年現在,8名のNASDA宇宙飛行士がいるが,彼らの健康管理を行なうグループも初期の医師1名とそのサポート3名という小さな体制から常勤医師7名,看護師1名,心理学関連1名,エンジニア6名に多くの非常勤専門家によるより大きな組織体制となり,宇宙ステーション時代に向けて国際調整,宇宙医学研究,そして本来業務である健康管理運用と忙しい日を送っている。Fig. 17に2005年現在の医学グループが置かれている組織体制図を示すが,現在の体制はいかに大きくなっているかがわかる。
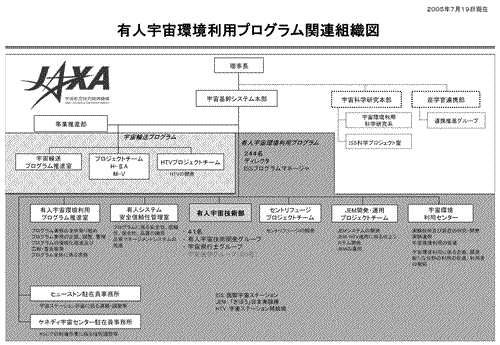 |
| Fig. 17. Organizational Structure of Space Environment Utilization Program in JAXA at 2005 |
C. 初期の厚生省出向医官の貢献
初期のNASDAでは医学・健康管理業務がマネージメント的に確立していなかったため,厚生省から出向した技官の土居は,その立ち上げに努力しただけでなく,将来のNASDAの健康管理,宇宙医学研究をするにあたって医学研究の現状調査を三菱総合研究所に委託,宇宙医学で問題となっている循環器系,前庭系,精神心理系,筋骨格系などシステム毎に日本の第1人者で委員会を結成し宇宙医学研究の現状をまとめた。実際には,調査検討委員会を組織し検討を行った。具体的には各委員は過去の宇宙医学文献などから現状をまとめ,問題点と今後どのようにしていくべきかという報告書を作成していた。これらの成果は1990年代までの世界の宇宙医学研究の現状をまとめたものとしてその後の貴重な資料となった。
 |
 Fig. 19. Astronaut taking training inside a chamber Fig. 19. Astronaut taking training inside a chamber |
| Fig. 18. Hypobaric Chamber |
次に出向して来た曾根には上記の資料を踏まえて,その当時ある宇宙医学研究や宇宙飛行士の健康管理用施設を宇宙ステーションにむけて拡充するという作業を担った。現在ある宇宙飛行士養成棟とその中のいくつかがその成果である。その中には宇宙飛行士の健康管理や医学選抜に必要な医学機材の整備とその部屋の確保,そして健康管理や訓練施設として使用されている低圧室(Fig. 18, Fig. 19),閉鎖環境訓練施設(Fig. 20),無重量環境訓練施設に併設された高圧チャンバー(Fig. 21)などが入っている。当時遠心加速度負荷装置やMRIなどの装置の設置も検討されたが,予算の関係からこれらについては実現しなかった。
その後,曾根の後を引き継いで来たのが,加藤で彼は後に述べるフロンティア共同研究の立ち上げに大きな貢献を,そしてその次の末光は放射線被曝管理の立ち上げに貢献した。その後も厚生省,そして厚生労働省からの医系の技官の出向は続いているが,最近となるのでその詳細についてはここでは省略する。
 |
 Fig. 21. Hyperbaric chamber equipped near Weightless Environment Training Facility |
| Fig. 20. Isolation Chamber |
D. 日本人宇宙飛行士シャトル搭乗時の健康管理
最初の毛利飛行士の飛行では,上述したように関口はL-0実験という毛利飛行士を被験者としての医学実験を実施したため,弓倉が実際の宇宙飛行中の健康管理運用を行なった。その際の具体的なシャトルの健康管理運用は彼の書物に譲るとして,基本的に同じと思われるその後関口が実際の飛行時に健康管理を担当した向井飛行士,若田飛行士,そして二回目の毛利飛行士の健康管理運用時の経験からその具体的な方法についてここで述べる。
1994年に向井飛行士は生命科学実験を行うスペースラブを使ったIML-2ミッションに搭乗,この時初めて関口は日本人宇宙飛行士を対象としてスペースシャトル飛行時の医学運用(健康管理)を担当したが,その前にOn the Job Training (OJT)としてIML-1飛行時にシャトル飛行時のNASAの医学運用の実際を経験して学んだ。それは,飛行直前からの健康安定化計画(後述),医学検査,そして打ち上げ時の医学支援,飛行中のミッション管制センターでの健康管理モニター,そして帰還地での医学支援,最後にジョンソン宇宙センターに戻ってきてからの飛行後の医学検査などからなっていた。
アポロ時代に宇宙飛行士が飛行直前に周囲の人から感染したと思われるウィルス感染症を飛行中に発症し,ミッションに少なからず影響を与えてしまったことがあった。その苦い経験からミッション前の1週間ほどを通常の人たちから隔離するというものが健康安定化計画である。隔離するといっても宇宙飛行士を飛行直前に完全に滅菌された部屋に入れるのではなく,一般の人たちとの接触を最小限にして,職務上接触しなければならない人たちとは,彼らの医学検査を行い,現在風邪などの感染がないことを確認してから接触を許可するというものである。これによって飛行中の風邪などの感染症の発症が非常に減ったといわれている。この医学検査は我々FSが行い,特に日本人の場合には搭乗する宇宙飛行士の家族の診察と医学検査をNASDAのFSが担当した。もちろん我々FSもこの検査をNASAのFSから毎回ミッション時に受けて合格しないと宇宙飛行士の健康管理担当にはなれないことになる。
飛行前に宇宙飛行士も簡単な医学検査を7日前,3日前,飛行直前と健康状況確認のため医学検査が行われる。我々担当FSは主治医としてこのような医学検査と診察を行うのみならず,この期間には彼らの健康状況を身体的のみならず精神的にも注意深く見守っていることも重要な任務である。宇宙飛行士らは3日前には打ち上げサイトであるケネディー宇宙センター(KSC)に向かうが,われわれ担当FSもKSCに向かい,打ち上げ前の健康管理を行う一方で,万が一に備えて打ち上げ時には緊急医療体制の中に組み込まれる。
打ち上げ当日,宇宙飛行士の最終的な医学検査,といっても簡単な問診程度だが,健康状態を確認した後に,宇宙飛行士は全員そろってシャトルに乗り込み,我々FSは打ち上げサイトに近いところ(5 kmは離れているが)で万が一に備えて救急チームの一員として待機する。打ち上げが無事に終わったことを見届けると急いでミッション管制センター(MCC)のあるテキサス州・ヒューストンのジョンソン宇宙センター(JSC)に飛行機で戻り,飛行中の医学管制を行うこととなる。JSCの管制センターまでNASAのFSはNASAの専用のジェット機に乗って移動するが,我々NASDAのFSは民間の飛行機を使って移動する,これには4時間以上かかるため,打ち上げから我々FSが到着するまでの間の医学運用は他のFSが行うことになっている。我々主担当FSが到着するとNASAのFSは3交代(現在は2交代)で,我々NASDAのFSは2名でほぼ日本人が作業している時間帯を中心に飛行中の管理を毎日約8-10時間交代で行った。MCCでのFSの仕事は主にミッション中の宇宙飛行士の作業のモニターが主である。特に船内環境の,酸素や窒素の分圧,炭酸ガスの濃度,水,有害ガスなどのモニターを行うとともに,無重量空間で宇宙飛行士が行う作業,特に危険物の扱いなどに注意している。
FS業務のハイライトは,1日1回の宇宙飛行士とFSの間で交わされる会話Private Medical Conference(PMC)である。これはプライバシー保護の下,1日の宇宙飛行士の健康状態についてFSが直接宇宙飛行士と会話するもので,FS以外の人は聞くことは許されない。そのため通常はMCCの中にFSのコンソール(Fig. 22)で健康モニターを行っているが,PMCの時にはプライバシーの確保された別室で実施される。日本人宇宙飛行士のPMCに関してはNASDAのFSが担当して行うことが許され,直接宇宙にいる宇宙飛行士と会話ができ興奮したのを覚えている。一方,船外活動である宇宙遊泳の際には宇宙飛行士の健康管理モニターはさらに詳細となる。心電図,宇宙服の中の酸素濃度,炭酸ガス濃度がリアルタイムでモニターされる,特に心電図はFSのコンソールの画面に直接波形が転送されてきており,我々は宇宙遊泳中の心臓の電気的活動をリアルタイムでモニターした。MCCでの我々の仕事は座ったままただモニターし状況を記録することだが,8-10時間かなりの緊張が強いられることになる。このような緊張下での仕事が10日から2週間続くため,ミッションが終わるとかなり疲労が蓄積したという感じを覚えている。
 |
| Fig. 22. Flight surgeon console in the MCC |
ミッションが終わりに近づき,帰還地に戻ることが決定すると,再び担当FSは代理のFSにMCCを任せて帰還地に向かう,これもNASAのFSはNASAのジェット機で向かうことができるが,われわれは再び民間の飛行機を利用するため時間がかかる。遅くとも着陸の1日前には帰還地(通常は打ち上げと同じKSC)に到着しておき,そこで再び入門証を獲得して翌日の帰還に備える。帰還当日はNASAのFSとともに宇宙飛行士を出迎える特殊な大型のバスに乗って待機する。これはアメリカのワシントンDCのダレス空港などで使用されている飛行機に直接接続できる乗客搬送用の大型バスを改造したもので,そのバスの中には簡単な緊急医療機器などが搭載されている。シャトルが着地して1時間ほど安全確認のためのチェックが終わるとすぐにそのバスがシャトルに接続してまずはわれわれFSと帰還時担当宇宙飛行士がシャトルの中に入る。FSはもちろん宇宙飛行士の健康状態のチェックをシャトルの中で簡単に行い,問題ないことを確認してから宇宙飛行士はバスに乗り移る。バスに乗り移った宇宙飛行士はすぐに厚くて重い与圧服を脱ぎ,宇宙飛行士の制服とも言われる青いフライトスーツに着替える。そこでFSは宇宙飛行士に簡単な診察によって起立や歩行などに問題ないことを確認して,彼らは今まで乗っていたシャトルの点検を行うためにシャトル周囲を回って報道陣などに挨拶したりすることになるのであった。これらが終わると再びバスに乗って今度はKSCの中にある,診療施設に向かい,簡単な医学検査と飛行後のデータ取りということになる。これが宇宙から帰ってきた直後の宇宙飛行士にとって結構大変な作業で,スケジュールがきちんと事前に組まれているものの1人3-4時間もかかり,かなりの負担になっている。これらがすべて済むとようやく宇宙飛行士は解放され,FSもとりあえずは帰還地での任務は終わり,次のJSCでの医学検査に移る。
着陸直後の検査が終わると,宇宙飛行士はNASAの専用ジェット機(ガルフストリーム機)でNASAのFSとともにJSCに向かい,われわれ日本人FSは再び民間の飛行機に乗ってJSCに向かう。飛行後3日目には規定の詳細な医学検査がJSCで行なわれる,日本人宇宙飛行士の診察・問診はわれわれ担当FSが問診表に沿って詳細に飛行中の医学的な事項について問診し,同時にテープにそれを記録していった。これは時間も結構かかり,問診だけで1時間は要したと記憶している。ここの検査で特に異常がなければシャトルの短期間飛行では宇宙飛行士は健康上問題無しとして次の年次医学検査まで医学証明が得られることになる。ただし多くの場合に飛行後の基礎的な医学データの取得実験が続いて行なわれるため宇宙飛行士はその後も1週間から10日くらいはある程度拘束されることになる。このようにしてシャトル飛行時の健康管理はNASAのFSの健康管理運用をお手本にして少しずつ実績を上げてシャトル運用時の日本人宇宙飛行士の健康管理を確立し,次の宇宙ステーション時の健康管理運用の参考としていった。
E. 医学室の発足
1985年に宇宙飛行士の健康管理を実施する医師として関口が初めて技術者集団であるNASDAに入り,とりあえず組織の中で宇宙飛行士の健康管理と宇宙医学研究の実施と支援をする小さなグループとしてスタートした。その後,そのグループの規模は徐々に人数が増えていったが,組織の中では正式に認められたものでなく,単に宇宙飛行士の健康管理と宇宙医学の研究をするグループというものであった。しかし,1993年にはこの医学グループと宇宙飛行士グループを併せて有人宇宙活動室が発足し予算上も少しずつ認められるようになっていった。関口が入って11年目の1996年には我々宇宙飛行士の健康管理と研究担当をする医師はNASDAのプロパーだけで5名,それと厚生省より出向の医師1名の計6名となり,医長や主任医長として予算上も認められるようになった。健康管理体制でも述べたように,翌年1997年,関口がNASDAに入って12年目にようやく宇宙医学研究開発室が予算上も認められるようになり,人員もプロパー7名,出向や研究補助員などの人員を加えると16名ほどの組織となり名実ともに宇宙飛行士の健康管理と運用上の宇宙医学研究をするグループとなった。この時点で関口を室長として,プロパーのフライトサージャンが4名,研究担当医師が1名,運動生理の専門家1名,精神心理担当1名,その他それらをサポートする技術者などからなった。
F. ISS国際健康管理体制の検討
90年代後半から予定されていた国際宇宙ステーション計画での宇宙飛行士の医学基準やその健康管理を如何にしていくべきかを検討をするため,1995年春にNASAを中心にESA, CSA, NASDAなどの参加国の医学担当者が,アメリカ航空宇宙医学会(AsMA)参加に併せて準備委員会として集まったのが最初であった。NASAからは,当時の医学運用部門の主任であったDr. Roger BillicaとDr. Sam Pool,それにNASAの医学支援会社の人たちが,ESAからはDr. Volker DamannとDr. Paul Kukulinski, CSAからはDr. Gary Grayと今は宇宙飛行士となったDr. Robert Thirsk,NASDAからは関口が参加した。ロシアは最初の会合では開催地がアメリカだったこともあり参加しなかった。当時NASAはISSの具体的な長期滞在に向けてMirを利用して経験を積むためのPhase 1と呼ばれる時期にあり,医学関係の調整はWorking Group(WG) 8と呼ばれるグループによりロシアとアメリカの二国間で行なっていた。このWG 8にその2国以外のISS参加国も参加して国際健康管理を如何にして行っていこうかという調整の仲間入りをして発足したのが,Multilateral Medical Operations Working Group(MMOWG)と呼ばれた会合で,第1回は1995年秋であった。この名前は1997年まで使われ,その後ISSの国際間の了解覚書(MOU)発行とともにMultilateral Medical Operations Panel(MMOP)と呼ばれるようになり今日に至っている。最初の会合では,今後このようなきちんとした体制が必要だという共通認識を持っただけで,具体的な検討は行わなかった。そのとき以来,国際健康管理組織はMOUに則って以下の3つからなっている,すなわち,Multilateral Medical Policy Board(MMPB)を最も上級の組織として,その下に同列にMultilateral Space Medicine Board(MSMB)とMultilateral Medical Operations Panel(MMOP)ができた。同時に医学研究の倫理的な面を検討するHuman Research Multilateral Review Board(HRMRB)も作られた(Fig. 23)。
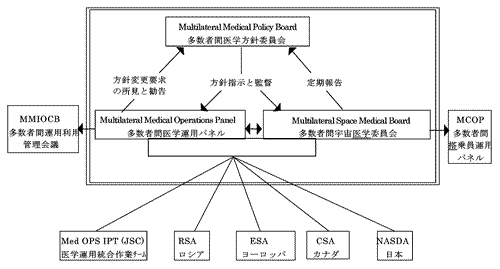 |
| Fig. 23. International Health Care Boards, Panels, and its Relation |
当初,最上位のMMPBはほとんど機能せずに,実際の健康管理運用で必要なMMOPが1年に2回,1回はアメリカでもう1回は各国持ち回りで開催された。最初の頃はロシアの医学運用を行ってきたDr. BogomolovとDr. Mogunは自分たちのこれまでの宇宙飛行士の宇宙滞在,特に長期滞在の健康管理には絶対の自信を持っていたせいか,かなり自分たちの意見を押し通そうという雰囲気がありありであったが,その後徐々に彼らも態度を和らげ,話し合いもスムーズになっていったことを記憶している。少しして,実際のISS滞在宇宙飛行士の認定をする段階となって,MSMBが機能するようになり,それに伴い医学基準も徐々にISSの現状に合うように見直しがされていったが,なにせ国際調整はなかなか事が進行するのが遅く,未だに調整すべきことも多いと聞いている。
III. 終わりに
日本における宇宙医学の黎明期から関口がNASDAに在職した2002年頃までの宇宙医学の変遷の概要についてNASDAを中心にまとめたが,まだまだ書ききれない部分があることはもちろん,さらにNASDA以外の部分に関しては不足している部分もあると思われ,その点についてはご容赦いただきたい。これが今後のJAXAの宇宙飛行士の健康管理運用や研究の一助となれば幸いである。また,これを書き残すにあたって多くのJAXAの方々やJAXAの医学グループを支援していただいた方に多大な協力を頂き,ここに紙面を持って深謝いたします。
| 1) | 関口千春,毛利 衛,村井 正,石井正則,谷島一嘉,中山 淑: 日本人宇宙飛行士の健康管理,宇宙航空環境医学31: 17-46, 1994 |
| 2) | Akima, H., Kawakami, Y., Kubo, K., Sekiguchi, C., Ohshima, H., Miyamoto, A., Fukunaga, T.: Effect of short-duration spaceflight on thigh and leg muscle volume. Med. Sci. Sports Exerc. 32(10): 1743-1747, 2000?3) 大島 博,関口千春,水野 康,向井千秋,福永哲夫,秋間 広,重松 隆,森 豊: 16日間の宇宙飛行が骨,筋肉に与える影響,日整会誌74(8): S1555, 2000 |
| 4) | 宇宙開発事業団技術報告書NASDA-TMR-020001 |
| 5) | 宇宙開発事業団技術報告書NASDA-TMR-020002 |
| 6) | Watanabe, Y., Ohshima, H., Mizuno, K., Sekiguchi, C., Fukunaga, M., Kohri, K., Rittweger, J., Felseberg, D., Matsumoto, T. and Nakamura, T.: Intravenous Pamidronate Prevents Femoral Bone Loss and Renal Stone Formation During 90-Day Bed Rest. J Bone Miner Res 19: 1771-1778, 2004 |
| 7) | 関口千春: 宇宙飛行士の選抜基準,臨床スポーツ医学10 : 31-7, 1993 |
連絡先:
慈恵医大
宇宙航空医学
TEL: 3433-1111 (内線2295)
E-mail: chisekiguchi@jikei.ac.jp