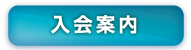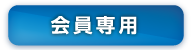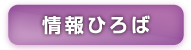富山県における病理細胞診の精度管理の取り組み
【質問事項】1.薄切の厚さの計測において,日常的に同一切片内で厚さのムラを経験するのですが,実施された検討の中で切片の計測部位(例えば,切り始めの部位や切り終わりの部位など)による厚さの傾向などはみられたのでしょうか.また,みられた場合は,どの様な手技に気を付ければ一定の厚さの切片が得られるとお考えでしょうか.
2.RGB解析について注意すべき点や,その他の特殊染色標本への応用例などがあればお教え頂けないでしょうか.
3.RGB解析を活用した内部精度管理を行いたいと考えております.日々の染色液の状態により染色性が変化していくと思われますが,その場合,どの様な手順(補正)で行えばよいかお教え下さい.
【回答】
1.1次サーベイと2次サーベイを行なった際に,質問や現地調査を行いました.その際に分かった傾向と原因と思われる事例は,まず,切り始めより切り終わりの方が厚くなる傾向が見られました.この傾向は,薄切室を持っていない施設に認められました.また,薄切室を持っていない施設の中には,麺出しができているか見極める為,窓際にミクロトームを設置している施設も見られました.これの施設は,室内の温度が一定ではなく,また,ブロックを0℃近くに冷やしているので,ブロックの温度と室温の差が高く,室温によってブロックの膨張が大きく薄切中も膨張しているためと考えられました.これの対応策は,ブロックを0℃近くに冷やす方法では,ブロックの温度はS字曲線を描き温度が上がりますので,頭出しをしたブロックを冷やして置き,素早く面合わせを行い,本切りを3〜4枚で終わらせるやり方があると思われます.ブロックの温度変化が無いか微小な時期に薄切してしまう方法です.この方法は素早さが必要とされ,熟練が必要です.また,大和光機工業のミクロトームであれば、パラクーラーPC-110があります.これは,ブロックを0℃前後でミクロトームに固定し薄切でき,ブロックの温度変化なく薄切できます.欠点は,結露が発生します.当院でも8〜9年前に若い技師が多く薄切が安定しなかったため,導入しました.もしくは,ブロックを冷却せずに,ミストで静電気を抑えて薄切する方法です.
もう一点は,切り終わりより切り始めの方が暑かったり,ランダムに厚い箇所があるものは,ミクロトームの刀台の一部やバーを持ったり握っている方の薄切で見られました.いくらベアリング方式でも腕の重さが刀台に係り,刀台の動きでかかる重さが変わることが考えられます.熟練の技師ならともかく,若い人での調整は難しいと考えられます.当院では,持つのではなく下から手を添え,一定速度で手前に引き寄せることを教えています.
2.RGB解析についての留意点といたしまして,まず,光度を一定(光量、NIKON製カメラでは解像度,露出時間,露出補正)にする点です.色が変わりRBGの数値が変わってしまい,比較できなくなってしまいます.顕微鏡カメラで示されるRBGの数値は一定の範囲の平均値です.一定範囲はある程度調整できたと思います.同じ組織構造をもつ箇所で対比がよろしいかと思います.組織の厚さの対比であれば,HE染色であればエオジンで対比するのが無難と思われます.測定箇所の近傍を数カ所測定し,類似数値を出す箇所を探し,測定場所を決定します.範囲内に核があるとヘマトキシリンも平均値に含まれてしまいます.
発表では肝臓組織でしたが,その2年後には大腸組織でも行なっております.大腸組織では,筋層を4点(両端,中間2カ所)で行いました.また,対比する標本は同一キャリアーで染色する事,保管は光をなるべく避けることが挙げられます.その他の特殊染色標本の応用例は当会ではありませんが,神奈川県の精度管理において,EVG染色のサーベイの際に,弾性繊維染色(レゾルシンフクシン)の染色の濃さの対比にRGB解析を使用していました.個人的には,明らかな白と黒以外にはRGB解析は使用できると考えております.特殊染色標本の応用例は,アミロイドなどの有無証明する染色においては,サーベイに使用できるのでは無いかと思います.
3.おっしゃる通り,染色液は日々変化してきます.ましてや,毎日使用する染色液は刻々と染色性が変化すると考えられます.染色液の内部精度管理にRGB解析を利用する場合は,まず,切片の厚さが同じであることが大前提になってきます.まず,幾つかの素性の違う組織を1つのブロックで作り,精度管理用に作成します.そのブロックを一番熟練した技師が30枚の未染標本を1日で薄切し,冷蔵保存します(室温だと、酸化が進み染色性に変化をきたす恐れがあります).毎朝,作り置きした未染標本を染色し,光度を一定(光量、NIKON製カメラでは解像度,露出時間,露出補正)にし,各組織の決まった場所(細胞質,核,粘液,筋層,間質)のRBGの値を測定します.数値化されることよりRBG各値の平均値や標準偏差が判りますので,試薬の変換は,各施設で決められた数値を超えた時に変化すれば良いと思います.各場所のRBGの3次元プロットで集約や分散が目視的にわかると思います.測定は“2”にも書きましたが,決められた場所のRBG数値は,一定の範囲の平均値です.拡大を変えて同一構造が範囲内に入るように測定するのがコツです.